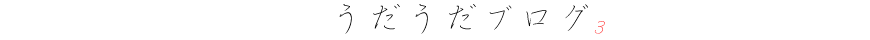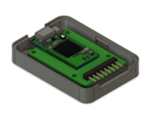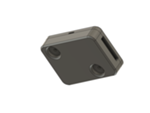2023年1月5日木曜日
NUCLEO-F439ZIでの実験の続きで
USB HiSpeed実験用の基板を製作した。
悩んだのがプログラム書き込み用の端子。
書込みにはSTLINKを使用するので4ピンの端子(SWCLK,SWDIO,GND,Vcc)があれば良い。
これとデバッグ用の
FTDI USBシリアル変換ケーブル用の
6ピンの端子をつけるのが、いつものやり方。
しかしNUCLEOでUSBケーブル1本で書込みとシリアル通信ができる
環境を憶えてしまったので 2本もケーブルを抜き差しするのは面倒に感じる。
最近のSTLINKでシリアル通信も使えるないかと調べると
STLINK-V3SET
ならいけるらしい。
しかし 9,400円もするしサイズが大きいし品切れだ。
いっそ、STLINKを自作すれば望みのものが作れるのではと
調べSTLINK-V3MODSという製品を知る。
STLINK-V3MODS
STLINK-V3MODSはSTMicroelectronicsの製品で
NUCLEOのSTLINK部分を小型にまとめたような基板。
開発基板に(ハンダ付けして)組み込んで使用することを
意図しているようだ。
Mouserに在庫があり
価格は1,196円。
安いが貧乏性なので基板に直接ハンダ付けするのには
抵抗がある。
使用しているCPUが
STM32F723で
本体基板で使用するCPU(STM32F405)より高級だ。
USB HiSpeedのPHYまで内蔵している....
ということで、必要な信号のみピンヘッダに引き出す
基板を製作し、使い回しの効く自作STLINKにすることにした。
引き出す端子は, SWCLK, SWDIO, Vcc(監視), TX, RX, GND, +5V(給電)の
7本だが市販の
ケーブルを使用したいので8ピンにする。
製作
年明け前に部品と基板が届いた。
STLINK-V3MODSは想像よりも小さい。
基板に組み込んで使えそうだ。
 |
 |
 |
| STLINK-V3MODS 上面 |
STLINK-V3MODS 下面 |
Mouserの送料が惜しくて5枚買ってしまった。(写真は4枚) |
ハンダ付けは何の問題もなく完了。
このまま使うのには抵抗を感じるのでケースを作る。
STLINK-V3MODSは3Dモデルのstepファイルが提供されている。
それらを使いケースを設計。
小型のケースは軽くてケーブルに振り回され安定しないので
ネオジム磁石を組み込んだ。
STLINK-V3MODS上のLEDと基板に書いた信号名が見えるように穴を空けた。
ケース上部と下部の固定は爪を出してその嵌め合いで行った。
今回はじめての挑戦だ。
何度か修正は必要だったが嵌め合いで固定できた。
 |
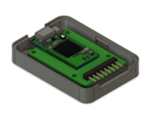 |
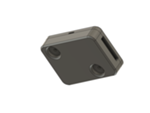 |
| ケースCAD画面 |
上部を取った状態。STLINK-V3MODSのデータはSTMicro提供のもの |
下面にネオジム磁石用の穴 |
 |
 |
 |
| ケース断面図 |
ケース上部は5回試作。前半は嵌め合いの調整。後半は穴のサイズと位置調整。 |
上部を開けたところ |
 |
 |
 |
| 下面の磁石 |
動作状態。LEDが点灯 |
基板に接続状態。 |
プログラム書込みテスト
 |
| STLINKコレクション。真ん中の中華のやつにシリアル通信機能がつけば良いのにと思う。 |
USB実験基板も部品を実装し
プログラムの書込みを試す。
最初、CPUが認識されなかったが
STLINK Utitityの更新後、書き込むことができた。
その後、シリアル通信をテストするがうまくいかない。
V3MODSの資料を見直して原因が判明。
使用している端子 T_VCP_TXが入力、T_VCP_RXが出力とある。
つまりTXは送信端子ではなく送信に繋ぐ端子(つまり受信)、
RXは受信端子ではなく受信に繋ぐ端子(つまり送信)ということだった。
この問題はマイコン基板等の端子の表記でよくおこるので、
最近はRXではなくRXO(RXだけど出力)とかTXI(TXだけど入力)などと
表記することがある。RXIやTXOは当然な気がするのでRX,TXで良いような
気がするが、
そうすると出力なのか入力なのかは資料を探さないとわからないことになる。
USB実験基板側の配線をジャンパーを飛ばし修正、シリアル通信が正常に
行えることを確認した。
最後に
次はUSB HiSpeedのプログラム作り、そして実験だ。
ゆっくり頑張ろうと思う。
しかし、STLINK-V3MODSのCPU,STM32F723はHiSpeedのPHY内蔵なのか。
欲しい。AliExpressの2,366円のやつ注文してみようか..