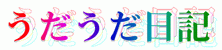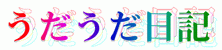- 2001年 1月 1日(月)
年が明け、TVを見ながら半田づけ初め。
後閑さんのページにある
FPGAの実験用基板
が ほぼ出来たところで寝る。
お年始廻りも終え、酔いも醒め机の上の整理。
FPGA実験基板と充放電器が鎮座している。
ここでFPGAに手を出すと充放電器が未完成のままになってしまうので、
FPGA実験基板はしばらく保留ということで、そこらにあった
透明ケースに入れる。
- 2001年 1月 2日(火)
昨日食べ過ぎで不調。
ごろごろしてすごす。
- 2001年 1月 3日(水)
体調も戻ったので
Ruby邪道編にあったRubyでExcelのデータをいじる実験を行う。
Win版Rubyのインストールは簡単にできた。
Excelファイル中の文字列を抜き出す実験を試みる。
Rubyは慣れないので Active-Perlで試すが、上手くいかない。
Rubyで試すとすんなり動いた。
Rubyのプログラムを参考にPerlのプログラムを修正すると、
こちらも動くようになった。
PerlやRubyでExcelなどをいじるのは、なかなか面白いが
上手くまとまった資料がないのがちょっとつらい。
その辺を整理しながらやると面白いかもしれない。
夜、こたつでノートパソコンを使いAVRのプログラムを書く。
AVRのアセンブラは書きやすい。
各ポートのデータレジスタ、入力ピン、入出力設定レジスタに独立して
アクセスできるのは便利。
- 2001年 1月 4日(木)
仕事始めで車で事務所に向かうが道はやたらとすいている。
世間はまだ休みか?
事務所は思った通り冷たい。
年賀状を投函するついでに藤崎八旛宮に初詣。
柏手の打ち方がわからん。
おみくじを買う。
*大吉*。
よしよし。
おもうがままになるそうだ。
●失物(うせもの) 高いところにあり。
憶えておこう。
夜、AVRのプログラムをしようとするが、
TVを見て 溜まった雑誌を読んでいたら時間がなくなった。
今年もTVは鬼門、ラジオを聞こう!
ラジオと言えは昼間
FMKに
まさきゆかが出ていた。
帰省中だったらしい。
- 2001年 1月 5日(金)
後閑さんのページを見ていて
PIC16F877応用NiCdバッテリ充放電器のページがあるのに
気がつきショックを受ける。
でも細かいところはダイブ違うなぁ。
ともかく私のも早く完成させよう。実用品だし。
▲
AVRのプログラムコーディング完了、
デバッグ開始。
- 2001年 1月 6日(土)
AVRのプログラムデバッグ中。
性格がいいかげんなせいか
なかなか思うように動かない。
アセンブラプログラムだけどprintfデバッグ
みたいなこと
ができるのが救い。
Chanさんの
AVRプログラムライタ プログラム AVRSSは使いやすい。
徐々に動くようになってきたが、ADコンバータとLCDディスプレイが
まだ動かない。
- 2001年 1月 7日(日)

AVR NIMH充放電器
|

|
AVRのプログラム完成、といっても まだ実験用のプログラム。
RS232C経由で電池の充放電/充放電電流の設定/電流の測定/電圧の測定/
LCDディスプレイへの表示などができる。
いずれスタンドアロンで動かす予定。
OPアンプとトランジスタを とりつけたところちゃんと動作しているようだ。
定電流回路が 一発で動いたのはちょっと意外。
パソコンからコントロールして、充放電特性をいろいろ計って見たい。
NiMHの内部抵抗って意外と大きいような気がするのよね。
ケースもそろそろ用意しよう。
またキャスター台をつくる。
45cm×50cmの板にキャスターを4個つけただけのもの。
電動ドライバーのおかげで簡単に作れる。
事務所のレーザプリンタLP-9200Sを載せる予定。
- 2001年 1月 8日(月)

キャスター台製作
|

プリンタを載せ移動
|
プリンタをキャスター台に載せ、移動。
良い感じ。
夜、AVRいじる。
Linux上のPerlプログラムから充放電器を操作できるようになった。
とりあえず充電プログラム(?)を作り、
電圧をはかりつつ、
0.1C(160mA)で10時間充電してみることにする。
ん? 10時間と言うと 明日の出社時間に
なっても終ってないことになるなぁ。
ADコンバーダにノイズがかなりのっている。
V-refやAVccをVccに直結しているので当然ではある。
この辺を改善する前に、Sleep Mode Noise Canceler
という機能も試してみたい。
▲
160mAの充電でも定電流回路のトランジスタ(2SA1940を使用)は
かなり熱い。 電源が12Vで電池が6Vぐらいだから
(12V-6V) * 0.16A = 1 W ぐらい。
ちゃんとした放熱器が必要そうだ。
PentiumIII 800MHz付属のやつが余ってけど、
ケースに収まるかどうかが問題。
▲
電流-電圧特性とか取って、電池の内部抵抗も計ってみたい。
電池ボックスのバネは鉄だから、結構 抵抗があるという話もあったね。
- 2001年 1月 9日(火)
起床後、充電をとめる。
7時間ぐらい充電した事になる。
電圧の変化を gnuplot でグラフにしたのが右の図。
ノイズが0.1Vぐらいのっているが、
電圧はそれっぽく変化している。
10時間充電したら、完了間際の電圧変化が見れたかな?
そのうち試してみよう。
いろいろ試せるのはいいけれど時間がかかるなぁ。
気長にやろう。
▲
出社途中 フジオカでケース購入。
小さめなのでちゃんと収まるか心配。
▲
仕事中に
ぷらっと オンラインで衝動買い。
金曜日には届くかな。
帰宅後、購入したケース(YM-200)に充放電器の基板を納めてみるが
小さすぎた。明日 1サイズ大きいケース(YM-250)を買って来よう。
▲
ADのノイズ対策をSleep Mode Noise Cancelerも
含めていくつか試したが効果はあまりなし。
▲
電池の電流-電圧特性を計ったところ、300mA超あたりから
定電流回路が不安定になることが判明。発振しているみたい。
特性から充電時の抵抗は約3オームぐらいと判明。
この中には配線や電池ボックスのバネも含まれている。
ちなみに電池は4本直列。
高速充電で1Aぐらい流すと無視できないなぁ。
- 2001年 1月10日(水)
出社途中 フジオカでケース
YM-250を購入。
ついでに 部品ケース
ホーザンのB-10と2SC1815Yも購入。
▲
夜、定電流回路を調べる。
オシロスコープで見ると数MHzぐらいで発振していた。
おそろしや。
2SC1815を使い定電流回路をオリジナルの回路に戻す。
これで電源回路の容量(1A)ぐらいまで普通に流せるようになった。
▲
ケースに基板等をならべ、配置を検討。
板金加工は週末だな。
- 2001年 1月11日(木)

シャーシプラグ
|
出社途中 フジオカで
AC100Vのシャーシプラグ
(と言うのだそうだ)
、スペーサなどを買う。
3日連続で寄ってしまった。
AC100Vのシャーシプラグは
パソコン関連でACケーブルが沢山あるので便利。
穴開けは面倒だが良く使う。
しかし250円もする。
どこかでまとめて安く買えないものか。
と言ってもせいぜい10個ぐらいだけど。
▲
夜はなにもせず、早く寝る。
- 2001年 1月12日(金)

衝動買い3品
|

|
プラットホームから衝動買いの品届く。
インテルのUSB顕微鏡QX-3と
USBシリアル変換アダプタと
(IPv6の?)カメ。
このカメのぬいぐるみには
「KAME Project
http://www.kame.net」
というタグがついている。
公認カメ?
IPv6と何の縁もないけれど、とりあえず購入。
▲
夜、ビールを飲みながらトラ技とLinux Magazineを読む。
トラ技には懐かしや岡村廸夫先生
(と勝手によばせていただきます)
のお名前が。最近見ないと思っていたら,
こんなことやってたんですね。
- 2001年 1月13日(土)
寒い、会社から帰るとき 車のフロントガラスが凍り付いていて
前が見えない。 車が温まるまで待たされてしまった。
▲
充放電器はいよいよ明日ケース加工だ。
あと少しで完了だ。
次は何しよう?
いろいろ部品の手配もしようかな。
FPGA評価基板を使ってみようかな。
で、今日は久しぶりに雑誌パトロールを
書いた。
- 2001年 1月14日(日)
朝から板金工作。
ボケていて、左右を間違えて穴をあけてしまう。
修正でさらに穴をあけ、底面は穴だらけ。
基板、部品をとりつけ 改めてでかいと思う。
ヒューズケースが無いので配線は先延ばし。
▲
昼間外出するが寒い、天気はいいのに雪が舞っていたりする。
しかし積もる気配は微塵もなし。
- 2001年 1月15日(月)
雪積もる。
数センチだが熊本でこれだけ積もるのは数年ぶり?
道路もしっかり凍結していて、転倒する自転車多数。
車は慎重運転で大渋滞。チェーンを装着した車も多数。
わたしは徒歩で出社。フジオカに寄り部品を買う。
▲
夜、充放電器の追加ケース加工を行い、配線も完了。
あとは実験とプログラムの仕上げとケース加工の仕上げ。
先は長い!?
- 2001年 1月16日(火)
今日は雪は降らなかったが、寒い。
▲
夜、充放電器いじる。
動作がおかしいとおもったら配線が1本外れていた。
なんてこったい。
半田付しなおすとちゃんと動いた。
早く、残りのプログラムも作って終りにしたい。
- 2001年 1月17日(水)
アマゾンより
"Rich Dad's GUIDE TO INVESTING" 到着。
これは、ベストセラー
『金持ち父さん貧乏父さん』の続編。
同書のCDブックが目につき
通勤途中に聞くのも面白いかも、
本もあると聞き取れないときに便利よねと
両方注文したら本だけ先に来た。
(CDブックは3月発売だった、がび〜ん)
CDが来たらMDに録音して聞くために
ポータブルMDプレーヤーを買おうと思ってたりする。
最近の英語学習の本にはCD付属のもの多いので
いろいろ試せそうだ。
▲
雑誌で
ソニーの携帯 SO502iWMの広告を見る。
携帯で60分音楽を再生できれば MD持ち歩かずに済むし便利、
私の携帯はP501iでモノクロだし折り畳みではないし、
1年は経っているので機種変更もいいかも、
問題は 値段だよな
64MBのマジックゲート(メモリースティック)付属だから安くないよな と
ドコモショップに電話して聞くと 機種変更で
4万3千円 だそうだ。
とほほほほ、思い付きは あへなく消えて行ったのでした...
2万円ぐらいのMDプレーヤーを買おう!
MDLPだ!
▲
夜、充放電器のスイッチの配線をする。
- 2001年 1月18日(木)
朝、
アマゾンで
「XPエクストリーム・プログラミング入門」
発見。
"extreame Programming explained"の訳本かと思ったら
"Planning Extreame Programing"の訳本だそうだ。
とりあえず注文。
▲
昼、
シリコンハウス共立にPCカードソケットの在庫をFAXで問い合わせる。
そのあと
googleで
「PCカードソケット」を検索したら
若松通商で販売しているのを
発見。。
見た記憶があるのだが見つけることができなかった
幻のPCカードソケット。
メモリのコーナにあったとは。
▲
夜、充放電器に32KHzの水晶(RTC用)とLEDを半田づけ。
- 2001年 1月19日(金)
夜、充放電器 タイマー割り込みのプログラム。1秒毎にLEDを点滅させた。
- 2001年 1月20日(土)
コジマ電機はもうなんかキライになっちゃったなぁ...
MDプレーヤを求めて電気屋を回る。
コジマ電機 熊本店の駐車場に入る際 警備員(のアルバイトの女の子?)
に注意を受けて気分が悪くなる。
市内方向から駐車場に入るには、国道3号線を右折して入ることに
なるのだが、事故が多い(?)らしく、左折して入るようにと
警察方面から指導が入ったらしい。左折で入るには
どこかでUターンする必要があるし、ちょうど信号のタイミングが
よかったので右折で入ったら 警備員に止められて注意を受けた。
「今度来る時は ちゃんと回って来て下さい」と
言われて「二度と来るか」と思う。
この店は構造が悪すぎる。
目的のMDプレーヤー Sony MZ-R900は 32,800円と高いので、すぐに帰る。
前回 来た時も感じ悪かったし、2打数2安打。
コジマ電機とは相性が悪いらしい。
▲
つづいて ユニクロに うわさのモバイルバッグを見に行く。
最近大人気のユニクロは日曜日は第2駐車場までいっぱいで
なかなか来れなかった。 2,900円のモバイルバッグは予想以上に
よさそうだったので購入。
▲
激しくなる雨の中をヤマダ電機熊本南店へ。
Sony MZ-R900は なんと27,800円!
素晴らしい! とすぐに購入。
初めて デビットカードで支払った。
アマゾンより
「XPエクストリーム・プログラミング入門」 到着。
"Planning Extreame Programing"の訳本のはずが、
"extreame Programming explained"の訳本だった。
なんてこったい、
アマゾンのエディタレビュー間違ってるぞ。
まぁいいけど。
夜、AVRのプログラム。
16bitの演算や文字列への変換とかやりだすと
さすがのAVRもしんどいなぁ。
- 2001年 1月21日(日)
アセンブラプログラマの気持ちになって祈り、
AVRのプログラムを書く。
コーディングは疲れる。デバッグの方が刺激があって楽。
- 2001年 1月22日(月)

AVRプログラム中
|

|
自宅のパソコンのファンがうるさい。
起動してしばらくすると静かになるので放っておいたのだが、
いいかげんなんとかしようと外してみる。
CRC5-56をかけてみるが変化はない。
明日 交換用のファンを買ってこよう。
▲
AVRプログラムのデバッグ。
電圧と電流が表示できるようになり ちょっと嬉しい。
しかしまだまだまだコーディングが残っている。
- 2001年 1月23日(火)
仕事の打ち合せ前にアプライドに寄り、
ファンとモニターフィルター購入。
ファンは2,480円。それくらいするものらしい。
ケースは9,000円くらいなのにファンがこんなにするとは、
バラで買うから高いのか? それともケースのが安いのか?
▲
モニターフィルターを購入したのは
「あるある大辞典」を見て
+イオンが気になってきた為。
モニター回りでは +イオンが発生し、血行がわるくなり
疲れやすくなるそうだ。
本当かどうかはは知らないが、私がモニターの前で
疲れているのは事実だし、
フィルターはイオン対策に効果がありそうな気がするので購入。
3,480円。特に問題がなければもう1台分購入する予定。
+イオンを打ち消すには 水が良いそうだ。
番組では霧吹きとかやっていた。
てーんで、
水物のオブジェを
PCカードソケットのついでで 若松通商に注文。
夜、ファンの交換と AVRのプログラム追加。
ファンは当然だが静か。
充放電器は 経過時間と積算充電量も表示できるようになった。
だいぶそれっぽくなってきたなぁ。
- 2001年 1月24日(水)
う... 8cm角のケース用ファンって
ステップアップPCに 800円で
売ってあるじゃん(涙)。
ものぐさせずにちゃんと調べとけばよかった。
反省。
▲
夜、雑誌パトロールに
最近購入した雑誌の表紙だけ掲載。
中身は週末にでも書こう。雑誌をもう一度読みなおすことになるの
で、結構時間がかかるのだ。LinuxJapanも届いたのでこいつも掲載。
この号には私のLinuxでLEGOの記事が載っている。
次のネタは何にしよう...
後閑さんの充放電器と同じに
電圧測定時には電流を流さないようしてみる。
こうすると電池の内部抵抗や配線抵抗の影響を受けないのでgood。
よしよし、
こいつはCPUを使わないとやりにくい処理だぞ。
これでやっと 普通の充電器との差別化ができたかな。
▲
あとは、メニューを4つぐらい({高速,低速}{充電,放電})用意して
ボタンで選択してGO! ぐらいにして完成ということにしちゃおう!
▲
そもそもこの充放電器を作ったのは デジカメ(CoolPix990)用の
NiMH電池を秋月で買った充電器で充電しても10分程度で充電終了し、
ろくに充電できなかったから。
1月9日に この充放電器の実験で7時間充電した電池を
その後 CoolPix990に装備したら、いまだに使えていたりする。
実用品
(現実逃避だったという噂もあるが)
のつもりで作り始めたが、こんなに時間がかかるとは思わなかった。
(いつもは、完成させてないから時間がかからない?)
AVRのプログラムで時間がかかってしまった。
まぁその分AVRのプログラムに慣れたというのはあるが。
こんなに時間かかっちゃうと、どこぞに発表して元をとりたいと
思うのだが、わざわざCPUを積むメリットがいまいち見えない。
(CPU積んで賢くすると楽しそうという気分だけ
で作った... しかし賢くするには賢いプログラムを
かかなければならない、アセンブラで...)
ケースも馬鹿でかくなってしまったし、
そのうち USB付のコンパクトな筐体に作りなおして
パソコンと接続できて、ログもとれる充電器、なんちったら
完全に作りなおしだなぁ。USBを使えるようになったら
また考えよう。
▲
ということで頑張ってはやく完成させよう
という話でした。
- 2001年 1月25日(木)
共立電子にUSBコネクタとサンハヤトの変換基板(SOT→DIP)を注文。
共立電子は少量の見積り依頼に丁寧に対応してくれるので
恐縮してしまう。
変換基板は
MIC2250用。
なんとピン間0.65mm!
感光基板でも作れるかも知れないが、
エッチングが面倒だし、実験用なので注文。
▲
笑っていいともの
テレホンショッキングのゲストは井上陽水。
CDのプロモーションなのか最近 陽水はメディアへの露出が多い。
井上陽水とタモリが話しているのは面白い。
ちからの抜け具合がここちよい。
▲
夜、充放電の条件を決めようと
秋月のNiMH電池に付属してきた資料を読む。
- 2001年 1月26日(金)
夜、充放電器のプログラム。ボタン周りのプログラムを作る。
▲
朝まで生テレビで「なぜ日本は負ける戦争をしてしまったのか」を
議論していた。ちょっとだけ見たが、時代は変わったと思う。
日本の言論をチェックしている中国、朝鮮の担当者は
さぞや胃が痛かったことだろう。
田原総一朗に
「日本の戦争」を書かせた小学館の功績は大きい。
- 2001年 1月27日(土)
朝、ボタン周りのプログラムをいじる。
だいぶまともに動くようになってきた。
▲
若松より PCカードソケットとソーラー噴水到着。
石川氏から教えてもらって知っていたけど、
PCカードソケットは高密度(0.65mmピッチ)のカードエッジコネクタ
で使うのは大変そう。
やっぱりパーツコレクション入りか?
- 2001年 1月28日(日)

ソーラー噴水
|

|
ソーラ噴水を組み立てる。
ちゃんと水が噴き出す。
なかなか面白いが、
太陽電池では直射日光があたっている時しか動かないし、
動かしていくと水の量が減っていったりと
事務所で常に動かすにはいろいろ問題がありそう。
大きな器を用意したり、ACアダプタで動作させると良いかも。
▲
夜、AVRのプログラムを少し。 亀の歩みだな。
スイッチでの操作ができるようになってきた。
- 2001年 1月29日(月)
天気が良い。日も長くひところより暖かくなった気がする。
▲
夜、AVRのプログラム。
スイッチ周りのプログラムが快調で、
一気に完成するかと思いきや
はまる (涙)。
どうもAVRASM Ver1.3のロケーションカウンタ周りのバグらしい。
ChaNさんのサンプルプログラムにコメントがあったので存在は
知っていたが引っかかっていなかったので忘れていた。
ロケーションカウンタの計算が面倒。
明日にでも計算用のPerlのプログラムを作ろう。
- 2001年 1月30日(火)
朝、ヒゲを剃りながら
最近肌がいたい、乾燥肌かしら
などと思いつつ
シェーバーを見ると、穴の一部が大きくなっている。
隣の穴と連結してしまったものが 4個程あった。
うーむ、なんで〜?
とりあえず、替え刃を買って来よう。
fj.sys.ibmpcで
Windowsキー + "e"でエキスプローラ起動できることを知る。
便利。
▲
昼休み、車で山田電機に行き、シェーバーの替え刃購入。
某メーリングリストで インターフェース3月号にAKI-H8に
リアルタイムモニタをのっけ1/35 タイガーIのラジコンを
コントロールしている記事が載っているという情報があったので
これも購入。
読んでみると 船木陸議氏(RT-Linux関連書籍で有名)の
のりのりの記事でした。
▲
夜、AVRのプログラム。今日は好調。
あとすこしで完成して欲しい。
- 2001年 1月31日(水)
昼休み散歩ついでに日教社(模型店)まで
タミヤの2001年版カタログを買いに行くが、
入荷するのは来月だそうだ。
▲
帰りにDos/V Power Report 3月号と
Rubyを256倍使うための本 極道編 購入。
RubyUnitで eXtreme Programmingを極めろ
だそうで、
RubyのTesting FrameworkであるRubyUnitについての本だそうだ。
とりあえず
XPのサイトというものがあることを知った。
Rubyは知らないのに256倍本だけ2冊も買ってしまったなぁ。
▲
夜、AVRのプログラムを書き、充放電器はほとんど完成した...
と思いたい。 一応、本体だけで充放電ができるようになったはず。
あとは、ゆっくりテストをしながら、資料を整理しよう。