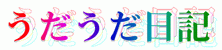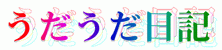- 2002年 8月 1日(木)
Olimexから基板出荷の連絡。
DSS(100mm×160mm)に、8枚面づけしていたのだが、
切断時、ミスで1枚壊してしまいました。
すみません。
とメールにあった。
8枚が7枚になっても、気にはならない。
▲
TVを見て、早めに寝る。
- 2002年 8月 2日(金)
仕事で修正版の基板を作成中なのだが、
WinBoardはつらい、仕事用も
EAGLEに乗り換えたい。
まず、WinBoardのネットリスト更新機能は
信用できないので使えない。
place fileで配置情報だけでも使おうと思ったのだが、
WinDraft(回路図エディタ)の
annotate(部品番号自動発生)機能が、
既存の部品番号も付け直してしまったため、
一部の部品位置が入れ替わる。
(涙)
あと、部品番号のシルクパターンの位置を調整できないという
問題もあるし、早めに EAGLEに移るべきだったかな。
でも、それには部品ライブラリの作り替えが必要なのよねぇ。
▲
人間ルータと化して、基板の配線を引きまくる。
この作業は案外嫌いではない。
単純作業が性にあってるのかも。
▲
配線途中に 回路ミスを発見。
windraftで回路図を修正し、
ネットリストを作り直し、
winboardでupdate netlistを実行する。
ちゃんとネットリストを更新できた。
うーむ、ちゃんと使えるんだ..

皿ネジ用に座ぐりぐり
|
- 2002年 8月 3日(土)
昨日、ホームセンターで購入してきた
座ぐり用のドリルを使って、
先週 作ったラップトップ台の皿ネジ化を実行。
良い感じである。
ドリルドライバーは便利だなぁ。
- 2002年 8月 4日(日)
先週作成し、昨日 改良した ラップトップ台の写真を整理し、
ラップトップ盤の製作のページを作成。
▲
Linux上で趣味のプログラミング。
集中力の低下を痛感する。
気力がなかなか維持できない。
▲
そんななか、かろうじて機能追加。
buggyな関数ができてしまったので、
UnitTestの導入を検討。
なんとか導入してみる。
▲
その関数の UnitTestで、
バグがどんどん見つかる。
デバッガでもテストはできるが、面倒なのでやる気が起きない。
テストケースをソースの近くに書いておけるというのが、いいなぁ。
▲
ちなみに、そのbuggyな関数は、線分と点の距離の二乗を求める関数。
画面上の図形をマウスで選択...などというときに使用する。
▲
プログラム全体をTest firstで作れればいいのだが、
あまりバグリそうもない関数だとテストを書く気にならない、
のはどうすればいいのかな?
そういうところはテストしなくて良い?
枠組みはできたので、ぼちぼち考えてみよう。
- 2002年 8月 5日(月)

小型VR 100円/個
|
電即納でVR(ボリューム)届く。
基板に取り付け用の小型で軸があるもの。
ドライバー等が必要な半固定抵抗ではない。
電即納は安いし、最新の部品が買えるのでとても嬉しい。
▲
雪ヶ谷の
アルプス電子といえば、
大学時代 お中元配達のバイトで
社屋内を さまよい歩いた記憶がある。
今日も趣味のプログラミング。
ラップトップ盤を使って
TVを見ながらプログラミング。
CMや興味が無いシーンで、プログラミングに戻るので
案外やりやすい。
といいながらいつまで続くかな?
▲
今日はなかったが、
考えがまとまらずに、すぐにコードがかけないような場面で、
作業が詰まってしまう。
こういう時は、紙にいろいろ書き出して
(
マインドマップ?)
整理すればいいのだが、それには机に向かわなければならない。
▲
そういう作業もパソコン上でやりたい。
いいアイデアプロセッサが欲しい、
いま、試そうとしているのがそれだ!?
と、話はどうどうめぐり。
▲
実際問題としては、
作業ノートとシャープペンをソファーの横に置いておくだけでも
いいのかも...
- 2002年 8月 6日(火)

マインドマップの本
|
今日も天気が良い。
これだけ日差しが厳しいと、わたしも日傘を刺したくなる。
▲
出社途中、大きな道の真中に 車が横転している。
背が高い小型車なので、横転しても妙に安定が良い。
胸ポケットには
EXILIM、
とっさに 写真を撮りたいと思う。
車体前方が潰れた車がもう1台、衝突事故のようだ。
怪我人は見当たらない。
さすがに運転中では撮れなかった。
時々、このサイトのアクセス状況を調べたりするのだが、
妙にアクセスが多いのが
DS1820 温度計と
マインドマップの本。
なんでだろう。検索で引っかかってるのかなぁ。
▲
評価キットDS1820Kまたはその代替品は購入可能か
という質問をうけたのでしらべてみた。
ご存知のとおり、ダラス・セミコンはMaximに買収されてたので、
情報や入手性が随分改善された。
Maximのサイトでしらべると、
DS1820はDS18S20に置き換えられ、
評価キットとしては、
DS1701Kというのがあるそうだ。
DS1701Kは$60,納期7週間
(DS1701Kの入手性と納期)
まぁでも、DS18S20を使うのなら、
TINI の方が面白そうだ。
イーサネット経由、Javaで DS1820等の1 wire interface chipを
使用できる。
オンラインで購入可能。
www.tini.orgという
日本語のサイトもある。
▲
実は... TINIを1つ持っている。
温度計を作ると言って、
石川さんからTINIを譲ってもらってから、
何もしていない。
(汗;;)
とりあえず、ケースにいれてネットワークにつなげばいろいろ
遊べそうだよなぁ。
- 2002年 8月 7日(水)
2号ほど前から、
Linux Journalを購読している。
12冊/年で $62
だったと思う。
薄くて私好み。 ^_^;
内容も面白いと思う。
^_^;;;
▲
あいまいなのは英語に自信がないから。
英語の勉強も兼ねて読んでいるわけ。
▲
そこで欲しくなるのが単語帳プログラム。
昔から何度か作っているが、満足なものはできない。
今作るなら、PostgreSQLとPerlでCGIとして作成し、
常時接続のサーバに設置すれば、
簡単に使いやすいものが作れそうだ。
そのうち作ろう。
▲
でも、そんなのって 既にあるかも、
アルクあたりにあったりして、
と見に行くと、単語帳はないが、なんかいろいろある。
つい
SVL12000語マラソンとか始めてしまう。
(無料)
▲
ヒヤリング道場 とか見ると、
マルチメディアによる教育の威力というものを
まざまざと見せつけられたような気になる。
▲
LYCOS翻訳も、
英文のメールの
言い回しが思い付かない時に使うようになったし、
便利な世の中だねぇ。
Lycosツールバーも使ってみようかな
- 2002年 8月 8日(木)
ななしのさんの
こころのとびらによると、
IPv6/v4 DualStack 汎用マイクロノード RS6なんちゅうものが
あるそうです。 TINIをそのままケースに納めたみたいですね。
値段が見積りをとらないとわからないというのが嫌だなぁ。
▲
旋盤関係の用語で検索をかけていて、
模型蒸機の部屋を発見。
ライブ奮戦記も面白いが、
雑記帳も面白い。
思わず読んでしまう。
▲
O編集長来社、いろいろ面白いお話を伺う。
- 2002年 8月 9日(金)
ついに、DRCをかけるとすぐにWINBOARDが死ぬようになってしまう。
泣く泣く
EAGLEに移行。
どうせ何時かは移行しなければいけなかったのだ、
と自分を慰める。
業務用で、サイズも大きいので Professional/Linux版のライセンスを
購入。(本体 $399 + schematic editor $399)
ひたすら、ライブラリの部品作り。
▲
偶然
..てまぁ、PC-Watchの広告ですが..
バトルフィールド1942というゲームの存在を知る。
この手のゲームは買ってもすぐ面倒でやらなくなるのだが、
たまには買ってみてもいいかな。
▲
ビールを飲んでTVを見て寝る。
最近このパターンが多い
ERは 今週と来週 休み。
替わりの
元ちとせの番組を見る。
- 2002年 8月10日(土)

基板到着 すぐ組み立て
|
AAF山本さんも
ROBO-ONEに出場するんですね、
黙って機体を作っていられるなんて凄いなぁ。
今日は予選ですね。
▲
Robo-oneのエントリー表を見ていると、自分も出場したくなる。
けど、
Bear-1は1月以来触っていない...
無線LANも使えるようになったし、
サブコントローラができたら、ちゃんと取り組もう。
▲
で、Olimexから基板がまだとどかない。
まさか、出荷を忘れて休暇に入ったのではなかろうな...
と、思っていたら、到着。
早速、組み立てて動かす。
いろいろと手間取るが、今回は回路ミスもなく、
動作する。 リセットの時定数がちょっと小さいかも。
- 2002年 8月11日(日)
めずらしく早起きする。
▲
AAF山本さんのページ経由で
Silf-H2計画を知る。
アクチュエーターがとてもカッコい〜い!!
▲
Bear-1を引っ張り出し、
今後の方針を考える。
とりあえず、足りない部品
(μPD16805とL-Card+用拡張コネクタ)
があるので、入手後再開となりそうだ。
▲
コントローラ間の通信はI2Cを使用する予定。
I2CコントローラをVHDLで書いて
XC95108で動かした
実績があるので、
これに 8バイト程度のバッファを追加、
さらに他チャンネル化したものを
FPGAに乗っけようともくろんでいる。
▲
PCF8584は L-Card+に接続し、
デバイスドライバーも作って
試したのだが、
転送速度が遅く、Linux側の負担も大きいので没。
▲
趣味のプログラミング、割と進む。
- 2002年 8月12日(月)
ROBO-ONE 第2回大会は
森永さんが
優勝されたそうです。
おめでとうございます。
パチパチパチ。
ニュースでもいろいろ出てきてますね。
ZDNetの記事、
PC-Watchの記事
▲
アマゾンに
Comic Studio Debut WACOMタブレットモデル
を注文。
▲
μPD16805がいつごろ入荷されるものか
ツクモRobocoN館に問い合わせたところ、
納期未定と返事が来る。
ELISshopで検索すると検索すると一応でてくるので、
そのまま見積り依頼を出すと、
今度は
μPD16805には16Pinと24Pinがありますが
どちらですかと問い合わせのメール。
なんか期待させてくれるなぁ。
必要なのは16Pinの奴ですと返事を出す。
- 2002年 8月13日(火)

ディスクグラインダー等購入
|
出社前に
ホームセンターサンコーに寄る。
早朝のホームセンターは、すいていてとても楽しい。
駐車場はガラガラで店内もスイスイ、レジ待ちも皆無。
▲
ø4のプラスチック-ネジを買いに行ったのだが、
1,980円のディスクグラインダーを発見。
この日限り、一名様2台までだそうで、
迷わず購入。いつ削りたくなるかわからないので、
切断砥石(3枚組 580円)、
鉄の平棒(4.5mm×32mm×910mm 310円)、
防護ゴーグル(680円)
なども購入。
▲
そのうち
チョッピリ折り曲げ冶具 L2を作ろう。
U城さんに、FPGAの半田付けが上手くいかないのですが、
と相談すると、
フラックスを使いなさい、とアドバイスを頂く。
ハケ付きの小ビンに入ったものが便利だそうだ。
フラックスリムーバも忘れてはいけない。
ついでに、テリーサという会社の半田を教えてもらったので、
ロジックデバイス
(ここも教えてもらいました)
に注文。
w-fieldの半田比較のページ
- 2002年 8月14日(水)
お盆で墓参りということで休み。
でも EAGLEの基板のファイルをコピーしてきたので、
家でも基板の設計ができる。
▲
このところEAGLEをかなり使っていて
Tipsもたまってきたような気がするので、
EAGLEのページを作成。
- 2002年 8月15日(木)

Agilent 54641D(下)と54622D(上)
|
お盆だけどお仕事。
EAGLEで配線したり、 郵便局行ったり、 銀行にいったり。
郵便局も銀行も窓口が開いているので、休みという感じはしない。
▲
EAGLEには慣れてきて、どんどん使いやすくなってくる感じ。
遂に
Agilent 54641D 到着!
帯域350MHz,2GHzサンプル,アナログ2CH + デジタル 16Ch,
価格は100万円くらいだが、6年リースで 16,000円/月ぐらい。
▲
写真の上は、
つなぎでレンタルしていた
54622D(帯域100MHz,200MHzサンプル)で、見た目は同じ。
レンタル料は 58,900円/月でした。
結局 2ヶ月借りて、明日返却予定。
- 2002年 8月16日(金)
真面目に仕事をする。
▲
L-Card+の拡張コネクタ到着。
このコネクタは
プラットホーム・オンラインには表示されませんが、
プラットホームから購入可能だそうです。
▲
プラットホーム・オンラインの検索機能は変だなぁ。
"L-Card+"で検索すると関係ないものが96件も表示される。
keywordが悪いのかな。 "16M"だと、18件で先頭が"L-Card+ 16M"だし。
▲
ちなみに、L-Card+関連商品は、
マザーボードのページにあります。
▲
帰宅後、風呂入って、ビール飲んで、TV見て寝る。
- 2002年 8月17日(土)
AAFおぎちゅーの
BBSでネジの話題があり、
実川製作や
アヅマネジを知る。
▲
短いネジが入手できないという話題なのだが、
私も基板の固定などに使うø3の短いネジを
ホームセンターで随分 探したが、見つけ出せなくて、
結局
カホで見つけたということがあった。
短いネジは電気部品屋にあるようだ。
▲
でもネジってそそる。
^_^;;;
子どものころから大好きだった。
大学受験で上京した時、初めて秋葉原に行き、
ネジをたくさん売っている店をみつけて
妙に元気がでた ...ということもあった。
▲
ネジは スペーサなどといっしょに
広杉計器から購入している。
50個単位で購入できるし、
対応も良いので気に入っているのだが、
金属ネジの品そろえがちょっと少ないので、
ネジの入手情報は助かる。
確かに アヅマネジの
超極低頭ボルトは魅力的だ。
使ってみたい。
とりあえず、欲しい。
^_^;;;
アマゾンより、
Comic Studio Debut到着。
このソフトの開発元の
セルシスが
日経ビジネスの最新号(2002.8.19)の
小さなトップ企業で紹介されている。
アニメ製作支援ソフトで
90%のシェア(本誌推定!?)
なのだそうだ。
もっとも、買い手のアニメ製作会社は数百社しかないそうで、
マンガ市場(プロ3000人、アマチュア 7万人)の市場を
めざし、 コミックスタジオを出したとある。
EAGLEで設計していたボードができあがり、
pcbexpressに発注。
EAGLEのpolygonによる塗りつぶし機能はなかなか良い。
気に入った。
- 2002年 8月18日(日)
ほぼ1年ぶりにテニスシューズ購入。
例によって年式落ちのものを約6,000円で購入。
店主によると、秋ごろ新モデルのをまえに、
毎年今ごろ シューズの値段がさがるそうだ。
▲
趣味のプログラムに励む。
なんとか、freetypeで字を表示できるようになる。
X-WindowでvisualがTrueColor時の、
RGB値をpixel値に対応させる方法がよくわからない。
適当にマスクしてシフトすればいいのだろうが、
シフト量はどこから取ってくるの?
▲
X-Windowも最初からTrueColorだけなら楽だったのに
...とか思ったりする。
- 2002年 8月19日(月)
お盆休みもおわり社会も動き出したようだ。
出社途中 パーツのフジオカに寄り
フラックス
(HOZAN H-721 280円)と
フラックスリムーバー
(HAKKO O13A 1,940円)を購入。
リムーバー高いなぁ。
▲
現品.comと
秋月にこまごまと部品を注文。
▲
μPD16805が
ロジックデバイスに あることが判明。
単価 500円で ちょっと高いが、注文。
- 2002年 8月20日(火)
夜、飲み会。
珍しく遅くまで飲む。
- 2002年 8月21日(水)
二日酔い。
- 2002年 8月22日(木)
現品.comより部品届く。
5V2A スイッチングレギュレータ 430円や
ステッピングモータ 580円や、
9pin RS232Cクロスケーブル 230円、
SMDの部品各種(2色LED,FET,VR)など。
▲
スイッチングレギュレータには、相手方のコネクタも付属している。
とても嬉しい。
ステッピングモータは、思っていたより大きかった。
将来つかえるといいなぁ。随分ステッピングモータをもっているけど、
まったく使っていない。
▲
つくば工房の
雨宿りの軒下掲示板によると、
現品.comの
電子部品のページにあるマブチモータ
FK-280SA は、普通のやつより
10倍ぐらいトルクがあるそうだ。
次の機会にでも買ってみたい。
- 2002年 8月23日(金)
エリスショップから見積り回答。
μPD16805GS(16pin) 335円/個 納期 30-45日、
μPD16805MA-6A5(24pin) 2,500個 400,000円 納期 30-45日
バラ売り不可。
40万円は出せませんね〜
▲
EAGLEで作っていた基板が発送されたらしい。
▲
ロジックデバイスより、テリーヌの半田とμPD16805GS(16pin)到着。
なんか部品がほとんど揃ってしまった。
でも、日曜から出張でしばらく手をつけられない。
- 2002年 8月24日(土)
出張準備などを行う。
- 2002年 8月25日(日)
東京へ移動。
秋葉原に行き、
日米商事でチップ抵抗のリールを物色するが、
スーツ+ネクタイ+荷物ですぐにキブアップ。
なにも買わずにホテルに向かう。
▲
夜、飲み会。
- 2002年 8月26日(月)
某大学(防大ではない)某センター見学。
工作室にマシニングセンターがあり、驚く。
- 2002年 8月27日(火)
泥縄で作った資料で、
ちょっと話をしたりする。
▲
泊まっているホテルは安いのだが割と広くて快適。
今回はノートパソコンを持参して、
暇な時間は何でも開発できる環境だったが、
ただTVを見るだけで、なにもせず。
- 2002年 8月28日(水)
出張の日程終了。
そのまま、秋葉原に移動。
荷物と背広をコインロッカーに預け、じっくりまわる。
日米商事でチップ抵抗のリールやら、
西川電子でネジやらコネクタやら購入。
JSTの
ZHコネクタが売ってあるのに驚く。
コンタクトも300円/100個で売ってあった。
▲
新横浜の高いところで飲み会。
VR系のいろんなボードを見せてもらう。
μT-Engineは凄く良さそうだ。
- 2002年 8月29日(木)
 やっと出張より戻ると、
荷物がいろいろ届いている。
pcbexpressに発注した基板も到着。
ベタパターンによる塗りつぶしが良い感じ。
でも、EAGLEのシルク幅がdefault 5milで、かなり薄い。
自作ライブラリはだいたい 10milに修正したのだが、
修正し忘れがいくつかある。 文字が全部 5milで 見にくい。
注意せねば。
▲
羽田空港で
運命の十年(柳条湖から真珠湾へ)購入。
すぐ読み終る。
この真珠湾以前の10年について、13人の意見が述べられていて、
いろいろ考えさせられる。
やっと出張より戻ると、
荷物がいろいろ届いている。
pcbexpressに発注した基板も到着。
ベタパターンによる塗りつぶしが良い感じ。
でも、EAGLEのシルク幅がdefault 5milで、かなり薄い。
自作ライブラリはだいたい 10milに修正したのだが、
修正し忘れがいくつかある。 文字が全部 5milで 見にくい。
注意せねば。
▲
羽田空港で
運命の十年(柳条湖から真珠湾へ)購入。
すぐ読み終る。
この真珠湾以前の10年について、13人の意見が述べられていて、
いろいろ考えさせられる。
- 2002年 8月30日(金)
事務所で、基板に半田づけ。
テリーサの半田とフラックスのおかげで調子良い。
▲
プリント基板の塗りつぶしで、Thermalsは指定しているのだが、
塗りつぶし幅を40mil(約1mm)で行ってしまったため、
細い半田ごてでは熱が逃げて苦労する。
今度は、もっと細くしよう。
▲
某所より
VR5500-ATOMなるものが届く。
morph3のコントローラに使われているやつである。
プレスリリースによると、
サンプル価格 15万円/台、 200個ロットで 8万円/台だそうだ。
じわじわっと、どんなもんか調べてみたい。
L-Card+より10倍ぐらい速くて、
Linuxも動くらしい。
- 2002年 8月31日(土)

VR5500-ATOM
|
台風15号が近いらしく、風が強い。
雨はまだ降っていない。
あとで、散発的に降った。
▲
事務所のプリンタ複合機
MFC-6800J
でトラブル。
突然、「エラーが発生した」と言われて
Windows-2000からプリントアウトできなくなる。
USBで接続しているので、
ケーブルを疑ったり、ハブを疑ったり、何度もリブートするが
現象は変らない。最後にふと、MFC-6800J側の電源を入れ直してみると、
あっさり印刷された。
MFC-6800Jは、FAX複合機で 24時間運転なので、何ヵ月も電源を
切っていない。そういう場合、USBまわりに障害がでたりするのでは
なかろうかと想像したりする。
▲
基板にフラックスリムーバを吹きかける。
半田吸い取り線のヤニもとれて、
コリャー良いと思ったが、
一部プラスチック部品が雲ってしまった。
スプレーの注意に、
アクリル樹脂、ポリカーボネイト、ポリスチレン、ABS樹脂などは
溶けるおそれがありますので、材質を確認の上御使用下さい
とある。今後は、プラスチック部品を取り付ける前に
使うことにしよう。
VR5500-ATOMを動かしてみる。
3階建て...一番下のボードは、コネクタをとりつけるためだけ
みたいなボードで、RS232C/Ether/USB(ホスト)などが出ている。
このボードは、状況に応じて もっと小型のものに変えるとかできそう。
電源をいれると、すぐにLinuxが立ち上がる。
CPUはかなり熱くなる。このままで動作は問題ないと聞くが、
やけど防止のため、フィンかファンを付けたほうがよさそうだ。