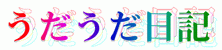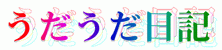- 2003年 5月 1日(木)
夜、VR4131DIMMボードのチェック。
DIMMモジュールやCoolRunnerの信号の確認をするが
間違いはみつからない。
評価ボードの回路図を調べていると、
モジュールのRFU/VCCにつなぎなさいと
書かれている信号に CPLDの出力が繋がれていることに気が付く。
オシロで確認すると、評価ボードでその信号は 0V になっている。
怪しい、明日問い合わせてみよう...って、休みかな?
実験するしかないか...
- 2003年 5月 2日(金)
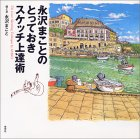 アマゾンから
永沢まことのとっておきスケッチ上達術届く。
時々スケッチの本が欲しくなる。
絵も描きたいなぁ〜
Virtual Penで?
いやいや 普通のペンで。
▲
Virtual Penと言えば、
コクヨの
ミミオ・パーソナルは 39,800円とちょっと高い。
18,000円のVirtual Penが安く思えてくる。
アマゾンから
永沢まことのとっておきスケッチ上達術届く。
時々スケッチの本が欲しくなる。
絵も描きたいなぁ〜
Virtual Penで?
いやいや 普通のペンで。
▲
Virtual Penと言えば、
コクヨの
ミミオ・パーソナルは 39,800円とちょっと高い。
18,000円のVirtual Penが安く思えてくる。
VR4131DIMMモジュールのRFU信号について教えてもらう。
これはモジュール上のFlashROMの可/不可を制御する信号で、
Highだと書込み可能になるだけで別に問題はないそうだ。
▲
付属CDにモジュールを使用するための最小限の回路図例が
載っているそうなので、印刷して調べる。
- 2003年 5月 3日(土)
朝からVR4131モジュール。
最小限の回路や評価ボードの回路を調べる。
プルアップがかなり足りないかと思ったが、
良く調べてみると GPIOとその他1本だけだった。
とりあえず、それらの信号を10KΩでプルアップしてみるが、
動作はあまりかわらない。試しに N-Wireでの接続を試してみると、
今度は接続できている。プルアップが効いたのだろうか、それとも
前回なにか間違っていたのだろうか。

モニタが動いた!
|

裏にVR4131モジュール
|
これで、モニターが動かないのは
評価ボードとのハード構成の違いのせい
という線も出てきた。 独自にプログラムを作成し、
N-WireでFlash-ROMで書き込む方法もあるのだが、
結構大変だし、モニターが動いたほうが嬉しいので
もうすこし粘ってみる。
▲
私のVR4131ボード( 名前つけようかな..)
の動作をオシロでみると、短いループに入って止まっているようで、
アドレスバスやデータバスでは周期的な信号が観測できる。
ここで、評価ボード独自のI/Oを触っているかもしれないと
IOCS0#というチップセレクト信号をみると、確かに出ている。
アドレスを調べ、評価ボードのマニュアルの照会の結果
LED表示レジスタとリセットレジスタへの書き込みと判明。
リセットレジスタというのが
とてもとても怪しい。
再度リセットしてやると動くと言うのだろうか。
しかし何度RESETボタンを押しても状態は変わらない。
メーカ提供のモニタプログラムは諦めて
独自にプログラムを書くしかないのかと、
付属CDにあるモジュール初期化プログラムの例
( いたせりつくせりだなぁ)
を読み始めると、見たような短いループがある。
LED表示レジスタとリセットレジスタに書き込み
ぐるぐる回っている。
▲
さらに調べると、SDRAMアクセス用のクロックの設定が
ある値にならないと、このループに入り、リセットを待つようだ。
さらに調べて
クロックの設定をレジスタを書き込んでいる個所を発見。
VR4131のマニュアルでそのレジスタを調べると、
設定後 RTCRST(一番強力)以外の
リセットを入れてください、とある。
そうか、やっとわかった、ということで、
ジャンパー線とCoolRunnerで、
リセットレジスタ(書込でRSTSWにパルスを発生)を作成、
CoolRunnerに書き込むと、
ついにモニタープログラムが起動した。
嬉しい。
しかし、CPLDは便利だ、
というかCPLD無しではこのモジュールは使えそうに無い。
- 2003年 5月 4日(日)
VR4131のプログラム環境を整備。
とりあえず、vmware中のLinux上に作ることにする。
ftp://ftp.ds2.pg.gda.pl/pub/macro/
から mipsel-linux-{binutil,gcc} などのRPMSをダウンロード
インストールするだけ。
▲
次にUARTからメッセージを出力する簡単なプログラムを書き、
これでコンパイル/リンクしてみる。
できあがるのは、Linux環境用のELFファイルなので
このままでは動かない。
デフォルトのlinkerスクリプトをコピーしいじり、
objcopyコマンドでMotorolla S-recordに変換する。
リンカーで直接S-recordを出力することも可能だが、
objdumpした時の情報が少なくなるのでこちらの方が便利。
▲
それっぽい出力になったのをobjdumpで確認したところで、
スタートアップルーチン crt0.Sにとりかかる。
こちらも、glibcのソースに含まれるデフォルトのcrt1.oのソース
(sysdeps/mips/elf/start.S)を元に始めるが、
デフォルトの PICのコードはややこしいので、
-fno-pic -mno-abi-callsをつけて逃げる。
きわめてシンプルなスタートアップルーチンになる。
▲
VR4131のモニターの機能でS-recordをダウンロードし実行。
メッセージが表示された。
ゴーストリコンをやる。
トレーニングを終え、やっとキャンペーンを始めたところだが、
操作はまだ憶えきれておらず、たまにZoomするつもりで、
弾を撃ったりする。 このゲームは時間的にせかされないので
良いのだが、 慎重に行動していると1プレイ40分と
かかかっていたりする。
夜中、TVで
未来少年コナンをやっていて驚く。
NHKアーカイブスで
1,2話と8話だけ放映されたもの。
夕方放映されていた再放送を大学の食堂のTVで延々みていたなぁ。
- 2003年 5月 5日(月)

本立
|
朝から本立を作る。
新しいプリンタを机の前の棚に移動したので、
今まで使っていた本立が入らなくなったため、作り直したもの。
自作だと、サイズを好きに合わせることができるのが便利。
▲
夜、VR4131のプログラムをいじる。
crt0.Sにbssの初期化を組込み
( してなかったのかよ)
、自作printfが動くようになった。
- 2003年 5月 6日(火)
仕事中うるさいと思ったら、
事務所近くの月極駐車場をコインパーキングに改造工事中だった。
これはちょっと便利かもとも思ったが、
駐車場の前の道って、一方通行なのよね。
行ってみて満車ということを考えると使いづらいかも。
▲
次は割込みハンドラだ、ということで
See MIPS Runの Exceptionの章を読もうとするが、
なかなか読み切れない。 気合いを入れてちゃんと読もう。
- 2003年 5月 7日(水)
アマゾンからの誘いのメールに負けて ( ? )
技術者が営業をきわめる本を注文。
この本が 1,450円で配送料が無料にならない
( 240円とられる )
のが悔しいと 他の本を物色しているうちに
RTLinuxテキストブック
(
CQ出版社のリンク)
をまだ買っていなかったことを思い出し、注文するが、
支払い方法が違うので結局 配送料は節約できない。
▲
夜、
ゴーストリコンをやる。
敵との交戦後、気が付くとB小隊が全滅している。
誰にやられたんだ? ミッションはなんとか成功。
▲
See MIPS Runを 読む。 良く書けた本だと改めて感心する。
- 2003年 5月 8日(木)
テニスに行って、
See MIPS Runを 読んで、
ゴーストリコンをやって、
録画したタモリ倶楽部を見て寝る。
楽しいなぁ。
- 2003年 5月 9日(金)
トランジスタ技術6月号届く。
特集は「はじめてのプリント基板設計」。
なかなかタイムリーな企画だ。
- 2003年 5月10日(土)
gccのインラインアセンブラをまた使う必要があったのだが、
忘れてしまっているので、
この日記をいろいろ調べる。
また同じことが起きたときのために、
gccのインラインアセンブラの使い方のページを作る。
▲
割込みハンドラの実験の下準備として
VR4131ボードのGPIOを動かしてみる。
▲
今日も
ER-VIIを見る。
楽しく見ているのだが、このシリーズは暗い話が多いような気がする。
- 2003年 5月11日(日)
VR4131の例外ハンドラを書く。
細かく実験を重ねながら作業を進め、
なんとかCの関数を呼び出しても
問題が起きないようになる。
mipsのアセンブラにも随分なれてきた気がする。
- 2003年 5月12日(月)
今日も、VR4131の例外ハンドラを書く。
亀の歩みだなぁ。
遅いけど、順調。
- 2003年 5月13日(火)
ゴーストリコンをやって、TV見て寝る。
- 2003年 5月14日(水)
仕事の基板を P板.com で作ってみようかと
いろいろ調べてみる。
納期6営業日だと、いつも使っている
PCBpro.comの送料込みの
値段よりは若干安い。
しかし、 準備するファイルが違うのが面倒だ。
▲
それでも頑張ってファイルを準備しようとするが、
ドリルのファイルであきらめてしまった。
スルーホール有りと無しでわけて、
それぞれにガーバーファイルとリストを作るのを
EAGLEでどうやればいいのかわからない。
あと、外形図を要求されるのもつらい。
▲
EAGLEのファイルを受け付けろとは言わないが、
Excellonフォーマットぐらい受け付けて欲しい。
まぁでも、EAGLEのファイルとか
受け付けるようになるんだろうなぁ。
VR4131の割込み処理もメドが立ったので、
モニタプログラムの作成を開始する。
とりあえず H8/Tiny用に作ったソースをいくつか持って来る。
次にUART用の割込みハンドラを書き始める。
- 2003年 5月15日(木)
トラ技の記事を参考にはじめて EAGLEのULPのプログラムを書く。
0.65mmピッチのTQFP-100ピンのフットパターンを書くのが
面倒だったのだ。
ULPでやると、とても簡単。
今後も活用しよう。
ゴーストリコンの「イージー」設定で
キャンペーンが終る。 次は「ノーマル」で挑戦だ。
▲
VR4131モニタプログラムで、コマンドインタプリタが動き始める。
さて、次は何を作ればいいのかな?
- 2003年 5月16日(金)
VR4131のモニタプログラムの次を考える、
と言ってもモニタープログラムが完成したわけではない。
どっち向きに完成させて行こうかという話。
▲
いろいろ検討した結果、とりあえず RTL8019ASの実験をするのが
適当だろうということになる。RTL8019ASに触るにはCPLDの
プログラムが必要ということで、検討すると
アドレス線が不足していることが判明。
CPLDに5本しか入力していなかった。
とりあえず、ジャンパー線で2本追加しよう。
我ながらいいかげん だ。
▲
RTL8019ASのデータシートを読む。わかりにくい。
何度か読む必要がありそう。
- 2003年 5月17日(土)

ヒートガン購入
|
りそなホールディングに公的資金注入のニュース。
2兆円規模って、もう金銭感覚が麻痺している感じ。
ところで、りそな銀行って何よ。大手らしいが...
と調べてみると、大和銀行とあさひ銀行が合併したやつらしい。
あさひ銀行って、どことどこが合併したんだっけ?
さらに検索して
銀行合併早見表(王貞治年表付)を発見。
協和+埼玉で あさひ銀行になったらしい。
あさひ銀行とイメージが似ている
さくら銀行は太陽神戸三井銀行で住友銀行と合併して
三井住友銀行になったのか。
▲
りそな銀行と聞いても、
ピンと来ないので不安感が煽られないのが不幸中の幸い?
って、私だけかな?
ICI に注文したヒートガン
HG-910SETが届く。
基板からICを吹き飛ばしてみたい。
▲
夜、飲み会。
となりの女性のグループがうるさくてあまり話せなかった。
- 2003年 5月18日(日)

トラ技とボード
|
のんびりとVR4131DIMMボードをいじる。
▲
未実装だった部品をはんだ付け。
ちゃんと起動することを確認。
▲
cpldに必要な回路を書き込み、
RTL8019ASにアクセスできるようになる。
レジスタを読み出すとそれっぽい値が出てくる。
▲
いよいよRTL8019ASのプログラムだ。
データシートがわかりにくいので、
トラ技の
目次データベースで NE2000関連記事を探し、
1999年7月号特集「インターネット時代のハード制御」、
2001年9月号特集「LANで制御するハードウェア」
などを見つける。幸い2冊とも手元にあり、
船田氏や落合氏の詳しい解説記事があった。
▲
これらの記事を参考に RTL8019ASの初期化ルーチンを書き、
試しに
秋月電子の
RTL8019AS付属のEEPROMに書き込まれたMACアドレスを
読み出すと頭の3byteは00-02-cb。
これを
ここで検索するとTriState Ltd.と出る。
正しく読み出せているようだ。
- 2003年 5月19日(月)
真面目に仕事をし、夜、テニス。
VR4131進捗なし。
- 2003年 5月20日(火)
iverilogこと
Icarus Verilogが結構ちゃんと使えるようなので、
CPLD/FPGAのHDL開発でverilogを試してみる。
XilinxのProject Navigatorに簡単なverilog記述を入力し、
Synthesizeさせてみると無事に終了。
シミュレーションを起動させるとエラーになるが、
これはVHDL用のModelsimしかインストールしていないせいだろう。
▲
実習Verilog-HDL論理回路設計を参考に
iverilogとvppでシミュレーションを行ってみると、これもちゃんと動く。
シミュレーション結果は$writeで出力もできるし、
gtkWaveでグラフィック表示も可能。
▲
iverilogはGUIなしのコマンドラインからの操作なので、
emacs+Makefileとの相性が良い。
M-x compile 後 M-x next-error で、エラーが発生した行に跳べる。
これがverilog導入の最大の目的。
verilog-mode.elも導入。
▲
VHDLよりVerilogの方が記述が相当短くて済むだろうと期待したが、
論理合成用に書くとそれほどでもなかった。
Verilogだといろんな機能を持ったテストベンチを楽に書けるのが
うれしい。
▲
実は昔 仕事でverilogを使っていた。
VHDLはCPLDと同時に使い始めた。
理由は
後閑さんのページでVHDLが使われていたことと、
良いVHDLの本があったから。
今後はVerilogかなぁ。
▲
embeded Unix Vol.3購入。
- 2003年 5月21日(水)
夜、VR4131のプログラム。
RTL8019ASでパケットを送信するプログラムを書いてみる。
プログラムを動かすと、LEDが一瞬光り、
パケットが送信されたような気がする。
▲
パケットアナライザで確認しようと、
WinPcapと
Analyzerをインストール。
観測してみるが、それらしいパケットは発見できない。
▲
そもそも、ケーブルでハブにつないでも、
ハブのリンクのLEDが光らない。
うーむ。
- 2003年 5月22日(木)
最近、仕事で使っているX-windows環境の安定性がよろしくない。
ウィンドウマネージャーのafterstepがよく落ちる。
ssh-agentからafterstepを起動するように変更してから
この現象が起きるようになったので、ssh-agentが怪しい。
linuxマシンとAstec-Xが動いているWindowsマシンの通信が
途切れた瞬間にafterstepが落ちているようだ。
通信が途切れるのはスイッチングハブが疑わしい。
電源がACアダプタなので、ケーブルが引っ張られたときに
電源断とか起こるのではなかろうか。
▲
これまでは頻度もたいしたことなかったので、
Astec-Xを起動し直していたが、
今日は何度も切れてしまい、我慢できなくなり、
ACアダプタを使わない電源内蔵タイプを買いに行く。
▲
ヤマダ電機に行くと、電源内蔵タイプがいろいろ置いてある。
値段はACアダプタタイプとたいして変わらず
3千円台からいろいろある。
これだけあるということは、
ACアダプタタイプは嫌われはじめているのだろうか。
ACアダプタ嫌いの私としては好ましい傾向だ。
▲
結局、10/100Mbps 8ポート電源内蔵の
laneed LD-PSW08C/ATを購入。
▲
ついでに スーパーフラットなLANケーブル
いわゆるきし麺ケーブル
も買ってみた。
小型の基板に普通のケーブルを刺すと、
ケーブルの重さで基板が安定しないのよ。
▲
ヤマダ電機への行き帰り、妙に道が空いていた。
走りやすくて結構なのだけど、何でだろう。
verilogでシミュレーション(仕事)。
verilogだとテスト用の疑似環境が簡単にかけるので便利。
シミュレーション速度もWindows上のModelSIMより段違いに速い。
こんな凄い環境が、
Freeで手に入るなんて....
VR4131基板をいじる。
ネットワークが上手くいかない件を
プログラムを修正したり、レジスタの値を見たり
いろいろ調べるがわからない。
▲
トラ技Special No.77 イーサネットのハードを理解しように
10BASE-Tのモジュラージャックのピン番号が載っていたので、
確認すると逆になっている。(汗;;;)
いろいろ調べてみるが、やっぱり逆のようだ。
RJ-45のライブラリを作るときに、
上下逆のものを参考にしてしまったらしい。
▲
パターンカットとジャンパー線で修正すると、
ハブのLINKランプが点くようになった。
Analyzerで監視しながら、
ARPのパケットを送信すると、ARPパケットが観測できる。
ここでARPパケットの中身の間違いに気づき、プログラムを修正すると
ARPの返事も返ってくるようになった。
よしよし
- 2003年 5月23日(金)
また EAGLEで基板設計を始める。
コマンドでSMDを配置する方法を覚えたので
ライブラリの作成が随分楽になった。
パッド位置がグリッドに乗らない部品は
エディタでスクリプトを書いて実行。
数が多かったら、ULPを書いてスクリプトを生成させる。
▲
VR4131ボード、RTL8019ASの割込み発生を確認。
秋月のEEPROMを装着するとINT4ではなくINT0に出る。
そのうちEERPOMの内容を書き換えてLEDの設定とか変更したい。
- 2003年 5月24日(土)

本日のお買い物
|
朝、VR4131ボードのGPIO割込みのハンドラを書く。
割込みを許可するために設定するレジスタが多くちょっと戸惑うが、
なんとか動いた。
きし麺ネットワークケーブルが
気に入ったので買い足しにアプライドへ。
いざ買おうとすると意外に高いので躊躇する。
ヤマダ電機ではこんなに高くなかったと思ったけどと、
ジャンクのAC100Vケーブル(100円)を4つと、
ヒートガン実験用にメモリーカード(100円)を1枚買って
ヤマダ電機に向かう。
▲
ヤマダ電機できし麺ケーブルの値段を確認すると、
アプライドよりは安いが似たようなもの。
前回はハブといっしょにポイント還元も使っていたので
値段をよく把握していなかった。
1本だけ買って帰る。
夜、ER VIIを見る。 このシリーズ、話が暗い暗い。
どうなってるんだろう。
- 2003年 5月25日(日)
怠惰な一日を送る。
▲
ゴーストリコンのキャンペーンを「ノーマル」で進める。
レーダーに敵が写らないのはつらい。
- 2003年 5月26日(月)
夕方、テニススクールへ行く。
雨上がりのせいか、遠くがきれいにみえる。
日が長く、7時を過ぎても明るい。
もうすぐ夏至だなぁ。
テニスは比較的好調。
▲
夜、VR4131のプログラム。
受信したパケットをダンプさせてみるが、なんかおかしい。
RTL8019AS読み出しのタイミングなどを調べる。
- 2003年 5月27日(火)
VR4131のプログラム、受信したパケットがおかしかった件は、
CRレジスタに書き込む値を変更すると直った。
ARPの処理部を書く。
▲
長いこと 2重リンクリストは嫌いで使っていなかったのだが、
linuxで使われている struct link_head が面白そうに思えてきた。
ちょっと使ってみようか。
- 2003年 5月28日(水)
 昼休み、まるぶんで
斎藤一人の絶対成功する千回の法則購入。
▲
眠かったので早く寝る。
昼休み、まるぶんで
斎藤一人の絶対成功する千回の法則購入。
▲
眠かったので早く寝る。
- 2003年 5月29日(木)
斎藤一人の本の残り半分を読む。
斎藤一人の話は、良性の宗教みたいだがなかなか面白い。
▲
タイトルの千回の法則というのは、
「幸せだなぁ」を口癖にして1000回唱えれば、
その言葉が影響自分の性格と行動に影響を与え、
うまく行くようになる、という話。
この話は前の本にも書いてあった。
試して害がある話ではない。
問題は1000回言えるまで憶えていられるかどうかということ。
▲
他にも試しても損はない面白い法則がいろいろ書いてあるのだが、
とりあえず気になるのは、
使い切った知恵は他の人に教えろ、
教えれば3倍になって返ってくる、
教えないと貧乏くさくなって失敗してしまう、
という法則。
自分も最近ちょっと出し惜しみの傾向あるような気もするので、
改めて、じゃんじゃん出していこうと思う。
ふと思い立って、壊れていたデジタル体重計をばらす。
中をみると、鉄の板にひずみゲージとおぼしき4端子のフィルムが
はりついている。ひずみゲージだったのか〜 なるほどねぇ。
壊れていたのはスイッチの動作不良だったようで、
組み直したら動くようになった。
しかし、別の体重計より 0.6Kg表示が重い....
校正用のハカリか、オモリが欲しい。
- 2003年 5月30日(金)
VR4131ボードは、pingの返事を返せるようになったが、
その後死んでしまう。
▲
今日も眠いので早く寝る。
- 2003年 5月31日(土)
ななしのさんの
こころのとびらで
モルフィー企画の商品販売が終了したことを知る。
結構お世話になったなぁ。
体重計の表示がずれていた件が気になり、
校正方法をいろいろ調べてみる。
標準の分銅の値段を
ここに発見するが、
20Kgだと一番安いやつでも 9万5千円!
▲
商売に使う秤は、計量検定所で定期的に検定を受ける必要があるらしい。
それはそうだろうなぁと納得。
そういう検定を受けた秤で、ダンベルの重さを計って、
校正に使用する手もあるなと思い付く。
▲
さらに検索を続け、熊本市の
市政だよりに、市の計量検査所が毎月小学校や市民センターで
特定計量器定期検査ということをやっているという記載を発見。
家庭用計量器の検査も行いますと書いてあるから、期待できるかも。
VR4131ボード。pingを返しても死ななくなる。