
|
写真日記
リンク集
旧コンテンツ
News,( US, UK)
はてなアンテナ
wikipedia
kick4wiki
kick4bbs
ジャパンネット銀行
ピンポイント天気
postMap
G-Tools
Kumaduino
うだうだ日記Index
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
うだうだ日記
前の90日分 | 次の90日分2001年6月20日 水曜日
ひさびさに、L-Card+の拡張バスの信号を 自作ユニバーサル基板を使って調べる。 ネットワークを使っていると、拡張バスの信号も 結構動いてくれる。 ▲ さて、次は FPGAを使ってI/Oポートを作ってみよう。 拡張バスにクロックは出ていないそうなので、 発振子ものせないといけない。
2001年6月19日 火曜日
雨が断続的に降る変な天気。 ▲ 夜、飲み会。 ▲ 最近、自宅での作業が進んでいない。 暑くなってビールばかり飲んでいるせいか... 反省しよう。
2001年6月18日 月曜日
ビールを飲みながらPCで作業。危険だ... ▲ 田中外相 アメリカ アーリントン墓地に顕花.... アーリントン墓地に参拝(?)しておいて、 小泉首相が靖国神社に参拝するのは反対するのか.. とからんでみたり.. ▲ Illustratorで図を描いてみる。 グリッドを設定すれば tgifみたいに絵がかけるぞ。 よしよし...
2001年6月17日 日曜日
自宅のWin2K環境でTeXを使ってみる。 思ったより、ちゃんと環境ができていて ちょっと驚く。 TeX使うためにLinuxで起動し直す必要はなさそうだ。 ▲ ROBOCONマガジン No.16 到着、表紙の富士通のロボットがカッコ良い。
2001年6月16日 土曜日
事務所のあるマンションでも、 KCNのCATVインターネットを使えるように なったそうだ。 ちらしが入っていた。 1Mbpsで4,900円/月(ケーブルTV無しの場合)。 今はフレッツISDNなので、 ほぼ同じ値段で 64K→1Mbpsに移行というのも魅力的。 まぁ、特に困ってはいないし、ゆっくり考えよう。 ▲ 新たなるロボット競技、 ROBO-ONE (ロボットのK-1なわけですね) というものが始まるということを知る。 どんな感じになるか楽しみ。 個人的には 2足より4足の方が面白そうだと思ってたりする。
2001年6月15日 金曜日
帰宅時、本屋で 村上ラヂオ 購入。 ▲ ERを見る。幸せ。
2001年6月14日 木曜日
照明といえば、 リファー ということで、 久しぶりに SD写真電気工業 のページを見に行く。 と、 蛍光灯専用リファーというのが 発売されている。 値段も従来のモノより安くなっている (38,010円(税込)→31,000円(税別)) し、 多少(?)暗くなるが、 発熱量が少ない (300W → 23W) のも嬉しい。 欲しいなぁ。 ▲ どうせ雨だろうと テニススクールを休むが、 雨は降らなかった... 天気予報は当たらないが わたしの予想もあたらない... 月曜日も同じパターンだったのよね... 悲しい。 ▲ 夜、自宅機のWin2K環境に このページ を参考にしながら、TeXをインストール。
2001年6月13日 水曜日
 小物用照明ライト! |
|
|
今日の思いつき! 白色LEDをLEGOで固定したもの。 小物撮影時の照明用。 ちなみに、LEDはブロックで挟んだだけ。 接着はしていない。 結構明るいが、照明範囲が狭め。 フィルムケースにLEDを数個固定し、 3脚にも取り付けることができるようにするといいかも。 白色LEDは15mA定電流ダイオードとのセットを 秋月電子から400円で購入したもの。 ▲ それにしても、 秋月電子のホームページの更新が少ないのは悲しい。 トラ技の広告を見た方が情報が新しい。 昔の、頻繁に更新していた あのころの姿に もどってくれないかなぁ... ▲ 秋月のページにバナー広告を載せている 現品.comの方が なんか秋葉っぽくて面白い。 何か注文してみようかな。
2001年6月12日 火曜日
 |
 こんな感じで作る予定 |
|
|
|
今日も、L-Card+用自作ユニバーサル基板をいじる。 信号名を jww (jwcadのwindows版) で描き、 ラベルシートに印刷し、はりつける。 こういう寸法の決まった作画にはjwcadは便利。 ▲ さらに シングルラインのICソケットを12Pin×8列装着。 これで、信号の観測が簡単にできる。 FPGA実験用基板で憶えて以来、よく使うようになった。 写真でソケットに指しているケーブルは サンハヤトのJUMP WIRE、ブレッドボード用のケーブル。 ▲ 次は、コネクタに出ている信号を まともに調べてみよう。 クロックが出てないのよねぇ。なにかするとでるのかなぁ。 FPGAで使いたいので、クロックが欲しいのだけど...
2001年6月11日 月曜日
 L-Card+ユニバーサル基板 |
 4枚で$99+$15(送料) |
|
|
|
事務所に来ると、クロネコヤマトのご不在連絡票が2枚。 さっそく電話して、再配達を依頼。 ▲ 昼前に、基板到着。 受け取り時に消費税を500円払うが、 価格は $99 + 送料 $15と 爆安! 帰宅後動作チェックだ! といっても、電源関連のショートさえなければいいのだが.. ▲ 部品が揃って来たので、 次の展開 (気が早すぎる?) のために FLEX10K30の144Pin TQFPの値段を ヒューマンデータに問い合わせると アッ!と言う間に返事が来て 驚く。 アルテラ製品はすべて寄り寄せ可能、 FLEX10K30A (EPF10K30ATC144-3)が8,000円だけど、 ACEX (EP1K50TC144-3)は4,100円でお得ですよ、 と有難い情報を頂く。 5万ゲートクラスかぁ。腕が鳴るなぁ。前職を活かせるか?
帰宅時、 トランジスタ技術7月号と 「なぜ、この人たちはお金持ちになったのか」 を購入。 ▲ トラ技では、 CPLD設計の連載が始まっている。 流行なんですね。^_^; 赤松さんの PCIボードの製作記事もある。 次号の特集は「実践入門 ロボット製作」だそうだ。 AAFARM Yamamoto氏の原稿ってこれなのね。 ▲ 本の話題をもうひとつ。 「聞く技術」が人を動かす。 多くの実例(悪い会話例と良い会話例)があり、 実際的で良かったです。お勧めします。 わたしにも役に立つはず。 また読み直す必要はあるなぁ。 7つの習慣をひとつも思い出せない今日この頃...
帰宅後、L-Card+用ユニバーサル基板をチェック。 電源のショートなどはないようだ。 コネクタのフットパターンが若干ずれている。 全長 31mmに対して、0.3mmぐらいずれている程度なので、 半田付けはできるが なぜだろう。 Gerberファイルの精度不足か? 次は気をつけなければ。 ▲ コネクタを半田付け、再度 電源ショートが無いことをチェックしたあと、 L-Card+へ装着。 電源投入で無事起動できた。
2001年6月10日 日曜日
UPSのTracking情報によると、 土曜の午後6時と今日の午前10時配達したが、不在だったとある。 ガーン.... 確かに昨日は 午後5時頃帰ってしまった... 明日、受け取ろう! ▲ 回路図入力を少々行う。 WinDraft(回路図エディタ)がよく落ちる。 セーブは一瞬だし、頻繁にセーブすると落ちないし、 10分おきに自動セーブされるので、 大きな問題にはならない。
2001年6月9日 土曜日
基板はまだ届かない... ▲ ユニクロでディパック購入。 2,980円。 (インターネット通販だと 2,900円) 迷うぐらいポケットがある。通勤用。 実は ユニクロのブリーフケースも持っている (使っている...)。 ▲ カメラのキタムラで また 3脚購入。 1,680円。
2001年6月8日 金曜日
 郵便小包で届く |
 とりあえずモノクロカメラ |
|
|
|
UPSのTracking情報によると、 基板は アンカレッジを発ち 大阪へ向かっているらしい。 手元に届くのは月曜日ぐらいかな。 ▲ 昼、 AMAZON Electronicsから CMOSカメラモジュール到着。 値段は $75, 送料は郵便小包で$12と安くて嬉しい。 ▲ カメラモジュールはカラーのデジタル出力だが、 モノクロのビデオ信号も出力されている。 とりあえず、電源をつないぐと、写った。 思ったより、画像は細かい。 ▲ 夜、UPSのTracking情報を見ると 午後7時14分に大阪の税関をでている。 ということは明日着くかも...
2001年6月7日 木曜日
UPSのTracking情報によると、 pcbproに発注した基板は 現在 カルフォルニアのオンタリオにあるらしい。 ▲ 事務所で FLEX10Kのデータシート (日本語版 ver4.02 142ページ)を 印刷したら、最後にピン配置も掲載されていた。うーむ。 ▲ 祝、コンフェデレーションズ・カップ 決勝進出。 ▲ 回路図を少し描く。
2001年6月6日 水曜日
朝、 WinDraft-PXのライセンスコード届く。 www.pcbpro.comの状況報告メールは来ない、が UPSから荷物発送のメールが来た。早いねぇ。 ▲ オリンパスのCAMEDIA C-1が良い感じで欲しいなぁと思っていたら、 C-100というのが発表になった。 世の変化は激しい。 ちなみに、今 持っているデジカメはCoolPix990。 こいつは重くて暗いので、もっとお手軽なカメラも欲しいと言うわけ。 C-100は単3アルカリ電池で1万枚以上撮影可能ってマジ? ▲ WinDraftで、USBアナライザ2号の回路図入力を開始。 まずは、FLEX10K10やDRAMなどの部品シンボル作り。 FLEX10K10のピン配置の資料が見つからずにちょっとさまよう。 アルテラの日本語サイトにはなく、英語サイトに見つかる。 この資料により、84-Pin PLCCのFLEX10K10には VCCIO端子が無く、 3.3Vと5Vのレベルコンバータとして使えないことが判明。 USBアナライザでは関係ないが、 L-Card+拡張ボードの方では使いたかったのでちょっとショック。 とりあえず、XC95108を3.3Vで使用して凌ごう。 いずれは 144Pin TQFP や 208Pin PQFPのFLEX10K10/20/30も使いたい。
2001年6月5日 火曜日
www.pcbpro.comより状況報告のメール届く。 現在 製造中で 明日出荷予定だそうだ。 ▲ 昼、 イーコンビより ホワイトボード 19,980円 届く。 昨日注文したもの。 福岡からなので翌日配達で嬉しい。 東京からだと、早くても翌々日配達になってしまう。 調子にのって、コピー用紙1箱も注文。 これを配達してもらうと嬉しい。 よしよし。 ▲ 夜、WinDraft-PX (ピン数無制限版 $495)を注文。
2001年6月4日 月曜日
 サトー電気より |
 ELISshopより |
|
|
|
朝から www.pcbpro.comに 基板を発注。 実際にWebからExpress1で注文すると、 必要とされるファイルが準備したものと違う。 苦労して作成した図面もREADMEファイルも必要ないようだ。 よくわからないが、ftpでファイルを送り、注文を完了。 ちゃんと受理されるか? 値段は4枚で $100ちょっと、だから安いなぁ。 ▲ サトー電気に、注文の品の件を電話で問い合わせる。 品切れのものがあったので、遅くなったが 6月2に発送したそうだ。今日ぐらい届くかな?
ということで、帰宅したら届いていました。 ELISshopに頼んだ4M DRAM (470円×8個) も届いていました。 これで USBアナライザ2号の部品がそろってしまった。 回路図を描かねば。 ということは WinDraft-PX (ピン数無制限版 $495)も必要か。
2001年6月3日 日曜日
まぁ、やっぱり日曜日はあまり活動しない。 自宅機にAcrobatとIllustratorをインストールして、 WinBoardの出力をpdf経由で取り込み、Illustratorで 基板の図面を描いてみる。なかなかきれいに描けた。 ▲ ひさしぶりに姪とドラクエ。
2001年6月2日 土曜日
www.pcbpro.comに出すデータを準備する。 GerberファイルとExcellon drill fileはなんなく出せるが、 Drawings(図面)をできればGerberファイルで出せと書いてある。 いろいろ試すが WinDraftでは出せそうにない。 PDFでもいいと書いてあるので、明日 Acrobat+Illustratorで なんとかしよう。 ▲ サトー電気とELISshopからいまだにものが届かない。 注文したのはELISshopが5/17、サトー電気が5/18? なんか変なもの注文しちゃったかなぁ。 来週電話してみよう。
2001年6月1日 金曜日
humblesoft.comのホスト移行完了。 humblesoft.com宛のメールもちゃんと届きます。 ▲ Jin Satoさんの MINDSTORMS情報局の電子工作掲示板で、 デジタル出力のCMOSカメラを AMAZON Electronicsから購入可能、 という話を知る。素晴らしい。 で、すぐ注文。 ▲ 発作的に 地図ソフト Mapfan.netを購入。 ホームページへの引用も可、というのが気に入った。 年間使用権 3,200円は高いか、安いか?
2001年5月31日 木曜日
humblesoft.com宛のメールが届かないのは、
サーバの設定が変わった為で、ちゃんと対応すれば届くよ、
と 同じレンタルサーバを使用している人に教えてもらう。
しかし、レンタルサーバの会社から来たメールにある
パスワードを入れても、設定のページにログインできない。
なんてこったい!
▲
明日から6月、このうだうだ日記にも
また1ページが追加されるのね、
去年の6月は何やってたんだろう、Dread Castで大戦略とかやってる、
掲示板とかまだ生きてるのかな... と見るとそこで
『DC版大戦略2001』なる文字を発見。
調べると 4月26日に発売されていたらしい。
前の『アドバンスド大戦略』は、面倒で諦めてしまったが、
今度はどうだろう。とりあえず買い?
アドバンスド大戦略2001のホームページは こちら→
http://add-dc.dricas.ne.jp/
▲
夜、Winboardをいじり、
L-Card+の拡張ユニバーサル基板のパタンが完成。
あとは、
www.pcbpro.comに受け入れてもらえるファイルを作りだ。
2001年5月30日 水曜日
う、humblesoft.com宛のメールが届かない。
しばらく調子がよかったので、安心していたらまたこれだ。
こんどこそ、サーバを移行しなければ..
△
夜、ドラクエのあと WinBoardをいじり、
コネクタ周りの配線を開始。
いじいじと配線をしているのが意外と楽しい。
はやく完成させて
www.pcbpro.com
朝早く目が醒め、Winboardをいじる。
△
サトー電気とELISshopから、
なかなかモノがとどかない。
△
ドラクエをやって、TVを見て寝る。
やる気が起きなかったので、
ドラクエVIIをやって、早めに寝る。
自宅機 Win2Kの設定の続き。
Meadowのフォントの設定がやっとまともになる。
WinBoardもインストール。
あと 3.3Vのレギュレータが届けば、
パターン設計ができる。
朝、
ヨドバシより
デジカメ ( Coolpix990) 用 ワイドコンバータ WC-E63 到着。
木曜日に注文したもの。 2晩で来るんだから優秀よねぇ。
サトー電気とElisShopは まだか?
朝から自宅機Win2Kの環境整備。
Meadowのデフォルトのフォントが大きすぎる。
フォントの設定の仕方がよくわからない(面倒)。
▲
夜、Win2Kの環境設定の続き。
Meadowのフォント設定、WinCvsの設定などを行う。
Meadowのフォントの設定はまだちょっと不満。
WinBoardのライセンス届く、
早速 自宅の Win98機に設定して、350ピン以上でもセーブできることを確認した。
と、ここまでは良いが、WinBoardを終了させて、再度起動すると
Win98ごと固まってしまう。うーむ、
事務所のWin2Kで試すと問題無い。
自宅機もWin2Kに変更か!
Win2Kは、安定してるし、割とコンピュータぽい
(^_^;)
ので 気に入っている。
帰宅すると秋月電子に注文した部品とLinuxJapan7月号が届いていた。
▲
LinuxJapanの「Linuxでロボットを作る」連載の著者は東北大学の熊谷氏。
って、
AAFARMのBBSでよくみる「くま」氏ですね。
今月の中身は、素のLinuxで処理を周期的に実行させる話...
て聞いた事あるなぁと思ったら、昨年の
ロボティックス・メカトロニクス講演会
(熊本であった)の チュートリアルで熊谷氏の話を聞いてましたです。
▲
LinuxJapanがどんどんハード寄りになってきてと楽しいなぁ。
▲
自宅機にWin2Kをインストール。
OSのインストールはすぐに済んだが、
自分の環境にするのに たくさん(?)のソフトを
インストールしなければならないので大変。
せめて、ソフトのリストでも整理しておけば次回楽なのに
と毎回思う。
(^_^;)
IVEXからメール。
昨日 注文時に入力した住所も郵便番号も照会できなかったので、
FAXで注文書を送ってくれ、だそうだ。
海外から私のクレジットカードの住所/郵便番号を照会すると
どんな答えになるのだろう。ちょっとわからん。郵便番号も
5桁だったりするのではなかろうか。 ということでFAXを送る。
▲
事務所からバスで帰宅する。
事務所には4年近く通っているがバスを使ったのは初めて。
事務所の前を時々走るバスが 自宅の近くを通るらしい
のには気がついていたのだが、
2時間に1本ぐらいしか走らないし、
コースが遠回り
(交通センター経由)
だし 乗らなかったのだ。
でも、45分の徒歩通勤疲れてきたし、いざという時(?)に
使えたら便利だろうと、時刻表を調べてついに乗ってみた。
すると、速い (20分) し、
安い(200円)し、
空いているし、
冷房までついていた、
ということで 今後使うようになるかも。
▲
Linux Japanのホームページによると、 7月号から
Linuxでロボットを作るという連載が始まるそうだ。
どんな記事だろう、楽しみだ。明日には届くかな。
IVEXに
WinBoard PX
( ピン数無制限版 ) を注文。
といっても、購入するのはパスワードだけで $495。
Webで注文できるが、処理は人手?
送られて来るのは next bussiness dayらしい。
▲
L-Card+のコネクタに出ている信号を調べる。
信号レベルは当然 3.3V。
拡張基板には 5Vしか渡らないので、
3.3Vは自前で作ってやる必要があるらしい。
拡張ROMボードを調べるとLCX245とか載っている。
Webで調べてみると、5V tolerantな 74*245だそうだ。
よくわかんないが3.3Vのレギュレータも載っているのだろう。
▲
3.3V/5Vの混在回路って 間違えるとラッチアップとか起こしそうで
ちょっと恐い。経験も無いので
どんなICを使えばいいのかもよくわからない。
(FLEX10K10にまかせるつもりだけど)
トラ技で特集して欲しいなぁ。
今日の
産経新聞 の
産経抄 にある
アメリカ大統領に靖国神社に参拝してもらおう、
というアイデアに感心する。
産経抄では、初夏の夜のゆめ として紹介しているが
実現したらいいなぁ。
▲
WinBoardでL-Card+の拡張基板のパターンを描いてみる。
どうやら 回路のピン数は700ぐらいになりそうで、
わたしの350ピン制限版では作成できないことがはっきりした。
まぁ無制限版が必要ということよね。
値段は WinBoard + WinDraftで $990。
Data Dynamicsで
IVEX COMPLETE PROを 129,000円で売っているけど、
Gerber Viewerって必要なのかな?
あいかわらず日曜日は何もしない。
ひたすら寝て過ごす。
出社途中、
それがぼくにはたのしかったから
と
くりやのくりごと
(文庫でない方は
こっち)
購入。
▲
最近、本の話題が多いのは、
電子工作関係があまり進んでいないという理由もあるが、
本当は
アマゾンのアソシエイト・プログラムの せい。
レポートで リンク毎のクリック数とかも見れて、結構 楽しい。
で、リンクを増やしたくなっているわけ。
▲
くりやのくりごと 読了。 面白かったです。
日本外交官、韓国奮闘記
を読む。 著者との見方の違い(わたしは右寄り)も感じるが、
それなりに面白い。知識も増えた。
▲
どうやら 田中真紀子 外相は
親中嫌米であるらしい。
困ったもんだ。
田中角栄の クチの悪い娘 に過ぎないのか。
加藤紘一氏も親中派 (中国シンパ? もっとすごい?)なのよね。
▲
親北朝鮮な政治家も与党内に多いというのは、
朝鮮統一の戦慄
に詳しい。
タイトルは過激だが 内容はクール。
▲
夜 ER Vを見る。幸せ ^_^;
USBアナライザ2号に向けて部品発注開始。
まず、
ELISshop にDRAMを発注。
あと
秋月電子と
サトー電気 向けに それぞれ注文書作成。
明日、発送予定。
▲
以前 購入していた、 AKI-H8/3664キットを組み立てる。
安い(2,000円)し、なかなか使いやすそう。
ラジコンのサーボが欲しくなって来て、
広告目当てで ラジコン雑誌を買って来る。
日本橋RCセンターとか
通販で買えるところがいろいろあるようだ。
1700円ぐらいのサーボを何個か買って見ようか。
▲
アルミ板も肉抜きするとイメージが完璧に変わる。
KHR-02ver1.1LW
は エラクかっこ良い。
ロボットのキーテクノロジーは板金加工か?
こんな加工手段がどうころんでも手に入りそうもないのが悲しい。
▲
動画(7.7MB)
も凄い。 自宅のCATV(1Mbps)からだと割に軽く見れる。
こんなのが作れるなんて、ひたすら感心してしまう。
仕事にいそしむ。
田中真紀子外相がアーミテージ国務省副長官との会談を
すっぽかしたというニュースを聞いて(遅い?)
なんか聞き覚えがある名前だと思ったら、
「海の友情 米国海軍と海上自衛隊」に
アーミテージ氏が国防次官補であったころの話が載っていた。
(p.207〜) 海軍兵学校の出身、ベトナム戦争で危険な任務に従事、
映画ランボーのモデルであるというまことしやかな噂もあるそうだ。
したいことはいろいろあるのに、だらけて過ごす。
▲
L-Card+拡張ROMボードの写真を撮る。
空母のようでなかなかかっこいい。
メッシュ部分にFLEX10K10を乗っけてみようと思ったが、
幅が1列足りないことが判明。残念。
L-Card+の拡張ROMボード をお借りする。
L-Card+に拡張ボードを載っけた状態というのは
なかなかカッコ良い。
ロボット用の安い拡張ボードとかできると良いなぁ。
▲
阿川尚之著 「海の友情 米国海軍と海上自衛隊」を読む。
デジタルオシロでのUSBアナライザ1号改の解析は大成功。
FIFOの扱いを間違っていることが判明。
回路修正の結果、SETUP, IN, OUT等のパケットもちゃんと
表示されるようになった。
こうなると、早速 USB機器を作ってみたくなる。
まぁ、USBアナライザ2号もUSB機器なのだけど。
▲
しかし、まぁ デジタルオシロは予想以上に強力であった。
あるとデジタル回路のデバッグが別世界のように楽。
借りてるうちにもっといろいろ作ろう。
▲
で、また前言撤回。
LCDのオシロも良い。
とても薄くて 置き場所に困らない。
寿命がちょっとぐらい短くても許すかも。
でも、どれくらいなんだろうなぁ。
バックライトとか5年くらいで切れちゃんじゃなかろうか。
AAFARM山本氏の犬小屋
(日報の左の推薦図書のbk1へのリンク)
に刺激をうけて、
アマゾンのアソシエイト・プログラムに参加してみる。
うだうだ日記中の書籍のリンクに アソシエイトプログラムの
私のIDを埋め込みました。
そのリンクからアマゾンに行って書籍を購入すると、
わたしに紹介料が入ります。
^_^;
いくら入るのかはよくわかりません。
面白そうだから、リンクを辿って購入してみよう!
^_^;
ちなみに
アマゾンへのリンクは4月の日記に 10件、3月の日記に4件の
あります。
▲
アマゾンと言えば、
お友達紹介プログラムで 500円のギフト券をもらっていたのを
思い出した。期限は 5月24日まで。
何を買おう
...と言いながら、アマゾンへのリンクを出現させるわけだ!
...アマゾンの術中にはまっているだけのような気もする...
で、
XPエクストリーム・プログラミング実行計画を購入。
ギフト券の使用も簡単でした。
▲
素晴らしいことに デジタルオシロ
(テクトロのTDS220 100MHz 2CH)
を貸していただけることになった。
大感謝であります> N氏。
さぁ USBアナライザ1号改の進展は如何に!
他の作業をしたいのに、
USBアナライザ2号について考え込んでしまう。
CPUとメモリの両方に接続するのにPLCC84のFLEX10K10だと、
I/0が59本で足りない。
将来的には144Pin TQFPあたりを使うことにして、
今回はなんとか84ピンでごまかして使おう。
DRAMを売ってるところを探そうとさまようが
若松通商以外なかなかみつからない。
64M DRAMのデータシートは
Hyundaiのサイトで発見。
16MDRAM以下は古すぎるのか見つからない。
NECと日立のDRAMが
エルピーダ
に移管され、 エルピーダには現行品種のデータシートしか
(まだ?)置いてないというのも
つらいところ。
▲
某氏より 安い(95,000円)USBアナライザが発売されたことを教えてもらう。
http://www.aubit.co.jp/
なかなかよさそう。
(ちょっと悔しい... ^_^)
USBアナライザを使いたい人はこちらを使うように。
もっと安いアナライザが欲しい人は気長に待つように...
^_^;
▲
エリスショップ
で 4MのEDOを単価470円 8個単位で売っているのが
目を引く。 メーカーはG-Linkとあるがどこ? と思って調べたら
台湾でした。ホームページは
http://www.glinktech.com/
GLT44016-40TC 0.8mmピッチ、
エリスショップからも一度買ってみたかったし
データシートもあるし いいかも。
▲
自宅で使用しているCATVインターネットが
256Kbpsから1Mbpsに増速したらしい。
PDFファイルをダウンロードしてたら 転送速度 76KByte/Sec とか
出ていた。朝なら本当に 1Mbpsでるかも。
でも、接続するとき若干待たされる感じがするのよね。
今のオシロスコープは大学入学時に購入した 10MHzのもの。
もう20年以上使っている。
(歳がバレる ^_^;)
次のオシロスコープを買ってこれをまた20年ぐらい使えば、
ほとんど一生モノよねぇ。
ちょっとぐらい奮発していいオシロスコープを購入しても
いいのかも...と
恐ろしいことを思いつく。
でもそうなると、LCDを使用したものはちょっと買えない。
20年ももつとは思えないから。
▲
仕事で必要になりExcel VBAの本を2冊購入。
いつもながらのどろなわである。
USBアナライザ2号の構成を考える。
CPUは AKI-H8の3048Fと3067Fのどちらにするか悩む。
秋月のAKI-H8/3067Fキットはピンヘッダが50PINしか出ていない。
CPUのバスは出ているのだろうか?
いずれは 3067Fをチップで使用したいが、
まだ実験機なので 100milピッチのユニバーサル基板上に組みたい。
FPGAはFLEX10K10,
RAMは
若松通商で売っている
64M EDO-RAM。
うーむ楽しそう。
サンハヤトの変換基板や 3.3Vのレギュレータも要るなぁ。
3箇所に発注だ。
▲
Jin Satoさんの
マインドストーム情報局を見ているうちに、
Digi・Keyという
パーツ屋さんにたどりつく。カタログ(PDFファイルだけど)が充実
していてなかなか楽しい。
FPGAのフィッティング後の回路での論理シミュレーションを
行って見ると動作がボロボロ。
(汗)
タイミング関係でいい加減な部分が多数みつかる。
clock schemeに基本的な混乱があった。
(まともに考えていなかった)
▲
昼から事務所へ。
連休中 メールがプロバイダーのスプールに溜るのが
耐えられなくなったため。
3日で115通、3.7Mbyte溜ってしまった。
プロバイダーは
biglobeで、
最大 999件/20Mbyteまで大丈夫らしい。
▲
FPGAの回路を修正する。
かなりまともに読めるようになった。
しかし、まだあやしい。
DATA0/1とACKパケットしか見えない。
ACKパケットが長すぎる。
ackパケットの後にINパケットがくっついている場合が
あるような気がする。 うーむ。
昨日のテニスのせいで、足がパンパンだ。
▲
FPGAの新しい回路のVHDLを作成し、書き込み実験。
論理シミュレータのおかげで、話が具体的になるので 設計が楽。
ぐずぐず作業したにもかかわらず、動作させるところまで進んだ。
▲
USBの通信を読み込ませてやると、SYNCフィールドを読めている
パケットもあるが、読めてなかったり、正体不明だったりの
パケットも結構ある。
読み込んだパケットの解析プログラムをPerlで作ってみる。
ついに作成中のFPGAの回路(USBアナライザになる予定)で
SYNCフィールドとパケットヘッダを確認できた。
まだ、テスト回路だが これで(ある程度)安心して
本番の回路設計に入れる。
▲
FPGAが気に入った。やめられませんなぁ。
家具のアオキより 事務所に
アーロンチェア到着。
ふっふっふ。
ついに買ってしまった。
価格は税別で 116,500円。
送料 1,050円と消費税込みで 123,375円。
明日から連休なのが残念。
調子がよければ自宅用にも買う?
▲
この日記のページの構成をちょっと変更。
まだ、試行錯誤中。
FPGAの回路を検討していて詰まる。
FF2個の簡単な回路のはずなのだが、
設計手順模索中という感じ。
FPGAの回路の回路図を WinDraftで描く。
FPGAだと端子位置を自由に決めることができるので
回路図がシンプルになる。
で、作業開始。既存回路の改造なので 比較的簡単。
改造完了する。
朝から嘉穂無線へ行き、じっくり在庫をチェック。
いやまぁほんとびっくりするくらい在庫がある。
サンハヤト製品をあそこまでそろえている店は他に知らない。
チップ抵抗まで売ってある。
レゴのパーツ(ターンテーブルやチェーン)も売ってある。
でも買ったのは ネジ(3φ x 4mm, 3φ x 6mm)と 3mmナット
を各200個とプラ棒。
Robocupを見に福岡工大へ。
百聞は一見に如かず。
見ないとわからないものですね。
大変、興味深い。
小型機リーグへの参戦を本気で考える。
▲
夜、Robocup関係者(?)と飲み会。
楽しかった。
▲
福岡泊。
デュアルヘッドにして以来、
Windows-Meがリソース不足で不安定になることが
よくあるので Windows2000インストール。
安定するかな?
▲
ヒューマンデータより
FLEX10K10とXC95108到着。
▲
明日は
robocupを見に 福岡だ!
JR九州のホームページに
時刻表を見にいったら、
経路探索機能で 到着時間から 乗り継ぎの電車の時刻が出た。
便利になったねぇ。
事務所の郵便受けに KCNのチラシ。
5月から CATVインターネットが増速し
256kbpsが1Mbpsになるそうである。
さらに2Mbpsのプレミアムコースも 月額 10,000円から 4,600円に
値下がりするそうである。
自宅で使っているCATVは 実測で 朝 256kbps, 夜 128kbpsぐらいしか
出ていない。朝は速くなりそうだが、夜は本当に早くなるか?
もっとも 事務所のあるマンションではCATVインターネットは使えなかった
はずだけど変わったのかな?
▲
L-Card+もあるし、CATVでどれくらい速度が出るのか測定して見ようか。
ヒューマンデータに
FLEX10K10とXC95108を注文。
すぐに使うわけではないが、
手元に現物があると資料も真面目に読める。
消費税+送料込みで 7,120円。
現在 実験に使っているのはXC9536なので
回路がすぐに容量オーバーするのではないかという不安も
購入の理由。
▲
GNU Autoconf/Automake/Libtoolの本 購入。
これで configureスクリプトも恐くない!?
FPGAの実験、
簡単な回路はちゃんと動いているようだ。
さて次はどうしよう。
Microdrive到着。
これでL-Card+のセルフ開発環境を構築できる。
セルフ開発環境用のケースでも作ろうか。
L-Card+は小さいからEtherのケーブルに引っ張られてしまうのよ。
▲
帰宅すると、絵葉書が届いている。
その追伸に
IBMのMicroDriveはL-Card+に入りません
と恐ろしいことが書いてある。
そんなことは買う前に言ってくれ
と思いつつも、MicroDriveをL-Card+に刺してみるとちゃんと入る。
L-Card+用のファイルシステムを作成しMicroDriveに書き込んで
電源をいれるとCFと同じように立ち上がる。
買う前に聞かなくてよかった。
▲
FPGAの実験回路をいじる。
携帯TVの電源をカーバッテリーからとりたいから調べて、
と頼まれたので調べる。
TVの電源は 9.5V 500mAとある。
電池6本でも動くらしいので、電源の幅はありそう。
レギュレータが入っているだろうから、
そのままカーバッテリーにつないでも動くんじゃないかと
思いながらも、安定化電源につないで調べてみると、
11Vぐらいまでは普通に動くのに、12Vにすると
電源がプツンと切れてしまう。
電源を切り、電圧を下げると回復する。
なんか電圧監視回路が入っているようだ。
結局 7809で 9Vの定電圧回路を作る。
▲
FPGA/USBの実験用の回路を作る。
これでいろいろ実験できるぞ。
L-Card+のオプションとして、
拡張バスのコネクタが発売されると教えてもらう。
該当のページを見ると確かにオプションに L-Card+拡張CN というものが
追加されている。標準価格がオープン、というのがなんだが、
素晴らしい。素晴らしい。
大変素晴らしい。
大感謝 >関係者の方々。
昨晩は 混んでいたのかダウンしていたのか自宅から
CATVインターネットに接続できなかった。
インターネットに接続されていないとできないことが多いのに驚く。
で、朝から VR4181のマニュアルをダウンロード。
30Kbyte/secぐらいでかなり速いとは思うのだが、
ASDLなら、1.2Mbps = 150Kbyte/sec なんだよなぁ、
とか思う。常時接続を始めて1年も経っていないのに、
世の中の変化は激しい。
▲
帰宅後、L-Card+をいじる。
なんとか、LEDを点灯できるようになった。
同様の方法で、他のI/O (AD/DA等)もいじれるようになるはず。
これで、いよいよ ロボットを作り始める?
とりあえず 福岡での
robocupを見てからはじめよう。。
▲
土曜日の熊本Linuxユーザ会
の定例会での発表の準備をする。
VAIOの外部ディスプレイのテスト、Magicpointのインストール。
mpeg_playのインストール、いろいろすることがあるが、
なんとかなりそう。
Laser5に、
「L-Card+でMicroDriveは使えますか」と
メールを出したら、
「きちんと確認はしていませんが、使えています」という返事が
すぐに返って来たので、
shopIBMに
MicroDrive 1G (税別 46,500円)を注文。
▲
デュアルヘッドでWindowsとX-windowsを同時に使えるようになったの
は良いが、ClickToFocusに慣れない。
Internet Explorerを更新後 Muleにカーソルを移動し、C-n,C-pを打ち、
プリンタダイアログや新規ウィンドウが開きまくって困る。
某メーリングリストで何とかならない?と質問したら、
Tweak-UIのX-Mouse機能というものを教えてもらった。
早速インストールしたが便利。
Microsoftもやればできるんじゃん、てな感じ。
L-Card+でinsmodを動かそうとしているのだが、
なかなかうまくいかない。
依然としてエラーがでる。
linuxceメーリングリストなどを読むと、ちゃんと動いているらしい。
何が問題なのだろう。
▲
そういうことを調べるためにも、
セルフコンパイル&デバッグ環境がほしいなぁ。
NFSでもいいのだけど、MicroDriveとか使いたいなぁ。
▲
ロボコンマガジン No.15到着。
西山一郎氏の「H8/300H Tinyを使ってみよう」
という記事が面白そう。
▲
insmodが動かない件をさらに調査。
クロスコンパイルした elfファイルのシンボルの数を示すパラメータ
の値が少ないことが判明。 理由はわからないが、
obj_load.cで 大きな値をいれたら、insmodできるようになった。
しばらくは、これでしのごう。
FPGA用にVHDLを書き、論理シミュレーションをする。
まだ簡単な回路だが、なんとか思いどおりに動くようになる。
10年以上ぶりに論理シミュレーションをやったような気がする。
パソコンで ちゃんと動くんですからたいしたもんだ。
▲
FPGAに回路を書き込み、実験する方法を検討。
▲
電子部品が溢れて収拾がつかないので、
大き目の部品棚とか欲しくなってきた。
でも、高いのよね。
とりあえず、ホームセンターにキャスター付の整理棚でも見に行こう。
出社前、紀伊国屋書店に寄ると
「最大効果!」の仕事術
という本が目に付いた。
先日購入した
なぜか『仕事がうまくいく人』の習慣と同じデザインだったからだ。
仕事がうまくいく人の習慣は面白かったし
効果もあった(とりあえず机の上は片付いた)ので、
最大効果にも興味を持ち、手に取って良く見てみる。
著者はちがうが 内容はおもしろそうだ。
仕事時間を減らして、高収入も自由時間も手に入れる
(WORK LESS,MAKE MORE)
方法を教えてくれるそうだ。
翻訳本で文字数は多いのに、値段は1,500円なので
文字単価は安いなどと考え購入。
▲
夜、ひさびさにL-Card+をいじる。
なんとか modutilをクロスコンパイルできたが、
insmodでエラーメッセージが出てしまう。
仕事でPerlのプログラムを書く。
すっかり packageとblessを使った
オブジェクトプログラミングがお気に入り。
データの局所化ができると、でかいプログラムでも楽チン。
でもライブラリを揃えれば、Cでも楽にいけるのよね。
あきらめたデュアルヘッドだが、早くも復活。
AKIBA PC Hotlineの
今週みつけた新製品に、
PCIのデュアルヘッドビデオボード発見。
ほほー、と思い さらに探してみると、
どうやら
innoのTORNADE GeForce2 MX 400 TWIN VIEW TV-OUT/PCI/64MB
17,800円と
MATROX Millenium G450DH/PCI/16MB BOX 16,800円で
PCIでデュアルヘッドできそう。
1000円差でメモリー4倍というのにも 心が傾いたが、
MATROXの方が評判がいいような気がしたので
G450DH/PCI/16MBを
Overtopに注文。
こんどこそデュアルヘッドになるか?
無駄使いばかりしているような気もする。
Windows-Meシステムのデュアルヘッド化は
ビデオカード同士の相性問題臭いので、あきらめる。
G400DH等を使えば簡単なのだろうが、
Bookタイプのベアボーンキット(MS-6209E)使用の自作機なので
PCIバスしかなくて刺せない。
サーバー機を整理し、1台浮かせて デュアルヘッド機に
グレードアップしたいと考えるが、なかなか大変なのよね。
▲
Adobe GoLive 5.0 トライアル版を インストールして試す。
なかなか便利そうだ。
HMTMを全部手で書くのも疲れて来たので、
ちょっと練習してみようと思う。
外出の帰りに
クマデンに寄り、
ビデオ カード SIS6326 8M PCIを購入。3,980円。
これで、Windows Meのシステムをデュアルヘッドにするつもり。
インストールはすんなりでき、ドライバーもインストールでき、
デュアルヘッドシステムのできあがり、と思いきや、
ウィンドウを移動させる途中に固まってしまう。
カーソルも固まる。Alt+Ctrl+Delも効かない。
新しいドライバーもインストールしてみるがかわらない。
なんなんだよぉ〜、Windows-Meが悪いのか?
ビデオカードの相性かなぁ。
アマゾンより
PANZER FRONT bizの攻略本と
Perl Cook Bookが到着。
土曜日には届いていたのだが、事務所宛だったので
今日やっと受け取れた。
朝からさっさと帰宅し、午前11時に到着。
その後 姪とドラクエをする。
天草へ家族旅行。
御所ヶ浦町の祭で鯛釣大会。
いけすの中の鯛を1人5匹まで釣れるのだが、
参加者はほとんど5匹釣っていたので、
市場で釣っているような物。
兄と甥が参加。
鯛は養殖物、 25cm〜30cmクラスで型も揃っている。
▲
夜は ローカルCM
(海外より海岸よね〜)で有名な
岬亭に泊まる。
実用Perlプログラミングを見ながら
Perlのプログラムに励む。
PANZER FRONT bizの攻略本がいつまでたっても
見つからないので、
アマゾンに注文。
ついでに
Perl Cook Bookも買って来るには重いので注文。
実用Perlプログラミングは取り寄せとか書いてあったので、
昼休みに紀伊国屋に買いに行ってしまった。
Perlのモジュール/クラス/組み込みまわりを勉強せねば。
実は昨日
Rubyプログラミング入門も購入したりしているが、
Ruby使いになるにはまだまだ時間がかかりそうだ。
▲
夜、ひさびさにニッケル水素電池の充電。
充電器を作ってから、
電池が長く持つようになった、
といっても 充電器が偉いわけではなく
それまで充電をミスしていただけ。
でも、充電器は便利、バカでかかったり、
蓋をあけないと使えないのが 難点だが ちゃんと使える。
エライ エライ。
今後、作り直すかどうかは微妙なところだ。
天気良し。
白川沿いの桜並木散歩するついでに
日教社(模型屋)に行き、
ウニモグ(オレンジ)発見。
15,800円。
うーむ、欲しい。
▲
モルフィー企画より
SL811HST(チップのみ)到着。
ジャングルTVを見ながら新ジャガを食べビールを飲む。
Astec-Xの試用期限が切れる。
これを機会に
CygwinのXを試そうかとするが、面倒ですぐ挫折。
とりあえず 次のAstec-Xの試用版をダウンロードして インストールしてしまう。
いいかげんに買わないといけないなぁ。
プラットホームで69,800円。
会社で使うので
個人向け販売 39,000円 というわけには
いかないのが辛い。
怠惰な一日を送る。
朝から原稿用の板金工作。
一気に2個作成。
前回(ニッケル水素充放電器)の失敗に懲りて、
慎重に行い 大きな失敗もなく完成。
あとはプログラムを作って、原稿もチャチャっと仕上げたい。
仕事がひと段落して 少し暇ができたので、
かねてより欲しかった 自社用のDBシステムを作ろうと考える。
サーバはFreeBSD上のPostgreSQLで迷わないが、
クライアントでいろいろ悩む。
参照だけを考えればWeb/CGIがベスト。
入力をGUIでやりたいので、ちょっと悩む。
Tcl/TkかそれともJava ?
印刷は Perl + TeX がベスト。
これは、Web上のCGIで印刷スクリプトをキックして、
ローカルプリンタに出力というのでもよさそう。
iモードJavaの話もあるし、この際Javaを憶えてみようか。
▲
仕事ではいろいろDBのシステムを作らされているが、
自社用のは今度で3つめ。
いろいろ未熟な点/不満な点は多いがそれなりに使えている。
2作目はシェアウェアのユーザ管理のDBだが、
クライアントは Emacs上で動くElispのプログラムだったりする。
情報がメールから来ることが多いので、
これが使いやすい。
▲
iモードJavaといえば
本屋で見かけたことはないが
iモードJavaプログラミングが 発売になっている。
アマゾンに注文しようか。
▲
とか思ったら、帰りに寄った本屋にありました。
買いませんでした。 ^_^;
春休みのせいか、朝から甥姪たちが来て勉強していた。
(感心だ。)
甥(小4?)は理科の電気回路の問題をやっている。
電池と電球を使った回路が6つぐらいあって、
(ア)の回路と同じ明るさになる回路はいくつあるか、
とかいうような問題だった。
話を聞くと、
プラスから出て来たのと、マイナスから出て来たのが...とか言っている。
電気が流れるイメージが出来ていなくて うまくわかっていないようだ。
電気回路は最初に実験をたくさんやって、
イメージを作らないと難しいそうだ。
電池ボックスと豆電球とワニグチクリップのセットでも 買ってやろうか。
初めて自分で考えた回路のVHDL記述を書く。
Meadow(Emacs)もVHDLモードでいろいろ手伝ってくれる。 ^_^;
Flip-Flop 2個の簡単なもの。
XilinxのWebPackでシミュレーションできた。
HDL Bencherというツールで入力パタンをGUIで作れるのが
気持ち良いが、すぐに容量制限を超えてしまった。
登録すれば無料でもっとでかいパタンを作れるよ、と出るが
登録サイトに接続できない。昨年12月に製造元がXilinxに
買収されたらしいので、変更があったのかもしれない。
昔は どうやって入力パタンを作っていたかと考えると
テキストエディタで0/1を書いてましたね。
VHDLでも同じことができるはず。明日挑戦しよう。
後閑さんのページで
USB通信テクニックのページを発見。
うーむ、私も頑張ろう。
▲
PICクラブ 第11回情報交換会の報告では
ロボット犬が興味深い。
9個のサーボを1個の16F877でコントロール。
315MHzの無線モジュールを搭載しコントローラで
無線操縦できるそうだ。
『電源OFFの時は、手足を伸ばして
腹ばいの状態ですが、電源をONにした途端、ガバッと起き上がったのには思わず
皆からオーっとばかりに感動の声がでました』
という報告は臨場感充分。
わしも早くサーボで
遊べるようになりたい。
「笑っていいとも春の増大号」を見る。面白い。
プリント基板作成成功!
藤商より感光基板などの部品到着したので
先週失敗した L-Card+の拡張基板製作に再チャレンジ。
感光、現像したところ ばっちり成功。
修正の必要なし。エッチングも完璧にできた。
あとは、勢いで穴あけとハンダづけを行い、
おそるおそるL-Card+のコネクタに押し込むと、
無理無くきちんと装着できた。
Laser5よりLinux Japan 5月号届く。
読者の声(Voice of Linuxers)に勇気づけられる。
気を使ってもらってるんだろうなぁ。
次の原稿も書かねば。
まだ何も書いていない。
材料は一応そろっている。
▲
FPGAの開発用にVHDLの良い教科書が欲しかったので
CQ出版社 長谷川裕恭著
『VHDLによるハードウェア設計入門』購入。
著者はSCハイテクにいたこともあるらしい。
なかなかわかりやすい。
▲
高校の同窓会の総会に出席。
気分良し。
PANZER FRONT biz.でベルリンをさまよう。
2001年5月29日 火曜日
2001年5月28日 月曜日
2001年5月27日 日曜日
2001年5月26日 土曜日
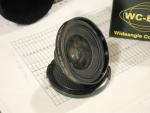
WC-E63到着

試しに1枚
![]()
![]()
2001年5月25日 金曜日
2001年5月24日 木曜日
2001年5月23日 水曜日
2001年5月22日 火曜日
2001年5月21日 月曜日
2001年5月20日 日曜日
2001年5月19日 土曜日
2001年5月18日 金曜日
2001年5月17日 木曜日

![]()
2001年5月16日 水曜日
2001年5月15日 火曜日
2001年5月14日 月曜日
2001年5月13日 日曜日

![]()
2001年5月12日 土曜日
2001年5月11日 金曜日

![]()
2001年5月10日 木曜日
2001年5月9日 水曜日
2001年5月8日 火曜日
2001年5月7日 月曜日
2001年5月6日 日曜日
連休最終日、だらけて過ごす。
ドラクエを5時間ほどやってしまう。
▲
夜、FPGAの回路を調べる。
パケットの中を見ると、けっこうちゃんと読めているように思う。
でも、なぞのデータがある。
▲
ああ、デジタルオシロが欲しい。
ソニーテクトロの
TDS220
(100M,2CH)を
オリックス・レンテックで1ヶ月借りると 29,800円。
10日で 約18,000円、買えば 218,000円(定価)かぁ。
▲
あるべきパケットデータを考えると、
トランスファーの最初のパケットが全部化けているようである。
USBアナライザ2号の製作を考え始める。
ちなみに現在いじっているのは1号改。

![]()
2001年5月5日 土曜日
2001年5月4日 金曜日
2001年5月3日 木曜日
2001年5月2日 水曜日

アーロンチェア
![]()
2001年5月1日 火曜日
2001年4月30日 月曜日
2001年4月29日 日曜日

買ったもの
![]()
2001年4月28日 土曜日

ロボカップ@福岡工大
![]()
2001年4月27日 金曜日

XC95108とFLEX10K10
![]()
2001年4月26日 木曜日
2001年4月25日 水曜日
2001年4月24日 火曜日

FPGA実験中
![]()
2001年4月23日 月曜日

MicroDrive到着
![]()
2001年4月22日 日曜日
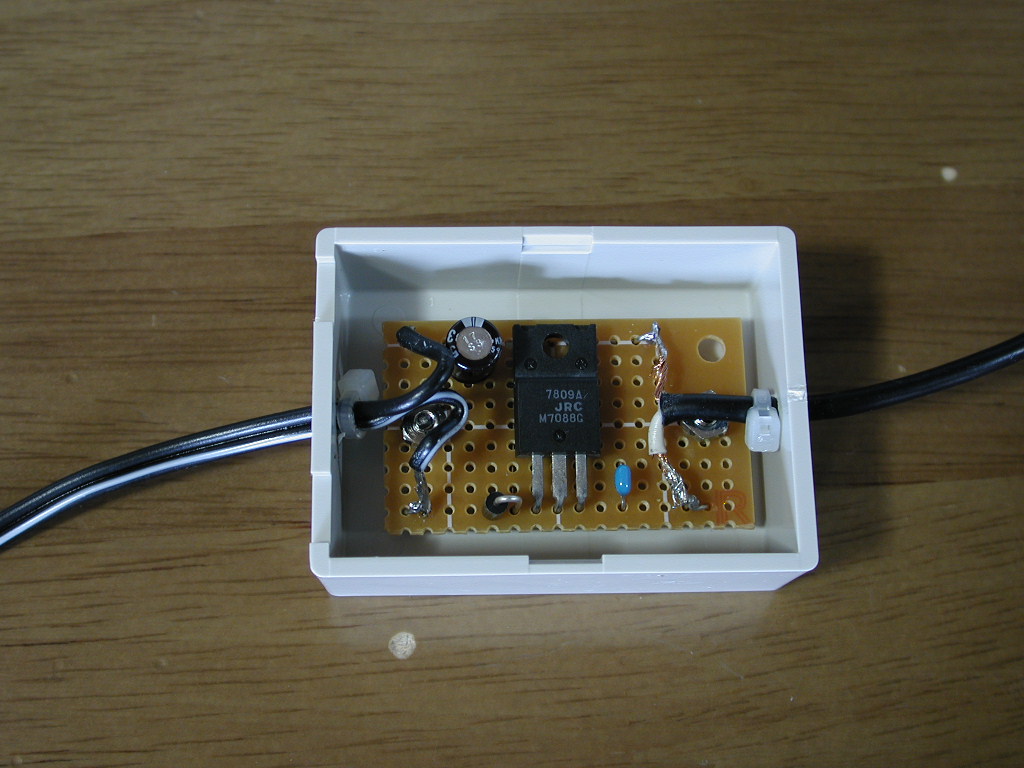
携帯TV用9Vレギュレータ
![]()
2001年4月21日 土曜日
熊本Linuxユーザ会定例会開催。
盛会でした。
展示物が多いので、準備も撤収も大変。
無線LANのハブは定例会でも懇親会でも便利でした。

展示物を自宅で確認中
![]()
2001年4月20日 金曜日
2001年4月19日 木曜日
2001年4月18日 水曜日
2001年4月17日 火曜日
2001年4月16日 月曜日
朝、ふと思いついて 部品+整理で検索。
ICIのページを見つける。
HOZANの部品整理箱 B-103が 9,820円かぁ。B-104だと 24,450円。
ちょっと考えてみてもいいかも。
でも
HOZANのホームページがあるとは知らなかった。
▲
昼、G450DH/PCI/16MBが到着し、ついにデュアルヘッドになる。
インストールはすんなりでき、
(当然だが)
フリーズもしない。
810内蔵のディスプレイ コントローラのドライバーも生きているので、
プロパティ上は トリプルヘッド。
▲
Asctex-Xをウィンドウモードで開き、右のディスプレイで
フルスクリーンにすると、右がUnix(FreeBSD),左がWindowsという
環境で使用中。 夢のような環境である。
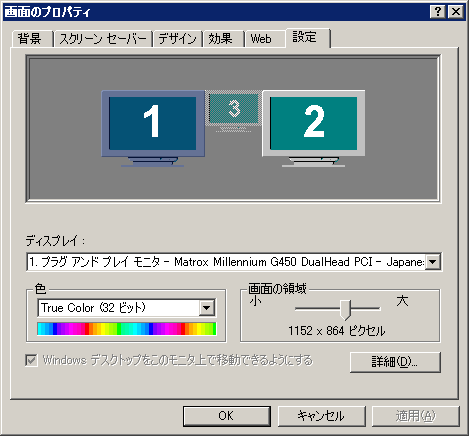
画面のプロパティ
![]()
2001年4月15日 日曜日
2001年4月14日 土曜日
2001年4月13日 金曜日
2001年4月12日 木曜日
2001年4月11日 水曜日
2001年4月10日 火曜日

購入したビデオカード
![]()
2001年4月9日 月曜日
2001年4月8日 日曜日
2001年4月7日 土曜日
2001年4月6日 金曜日
packageとかblessとか
初めて使う。
ネームスペースを区切れたり、
たくさんのデータを1つのオブジェクト
(ハッシュ?)に埋め込めるのは
気持が良い。
これで 複雑なプログラムも作りやすくなりそう。
▲
CAMEDIA C-1
が欲しくなって来た。
いま使っているデジカメはNikon Coolpix 990だが、
暗めで解像度が高いので 三脚がないと安心して撮影できない。
ついでに結構重いという問題もある。
で、いろんな意味で軽く写せる
サブカメラが欲しいと思っているのだが、
PC-WATCHの2つの記事
プロカメラマン山田久美夫のオリンパス「CAMEDIA C-1」レポート
と
オリンパス、38,000円の単焦点131万画素デジカメを読み直してCAMEDIA C-1いいなぁ。 と思っているのでした。 ベスト電気に 29,800円で売ってあった。 19,800円になるには相当時間がかかると思うのだけどどうだろう。 だから、待たずに買う?
▲
でも、
ウニモグとか欲しいものが他にいろいろある。
ガマン ガマン。
▲
夜、11時より NHK総合でER-V始まる。
嬉しい。
2001年4月5日 木曜日
2001年4月4日 水曜日

SL811HSTとサイズ比較のための74LS138(上)
![]()
2001年4月3日 火曜日
2001年4月2日 月曜日
2001年4月1日 日曜日
2001年3月31日 土曜日
2001年3月30日 金曜日
2001年3月29日 木曜日
2001年3月28日 水曜日
2001年3月27日 火曜日
2001年3月26日 月曜日
2001年3月25日 日曜日

L-Card+拡張基板 装着状態。

コネクタは1mmピッチの表面実装。

コネクタの装着感 良し。
2001年3月24日 土曜日
2001年3月23日 金曜日
前の90日分 | 次の90日分
